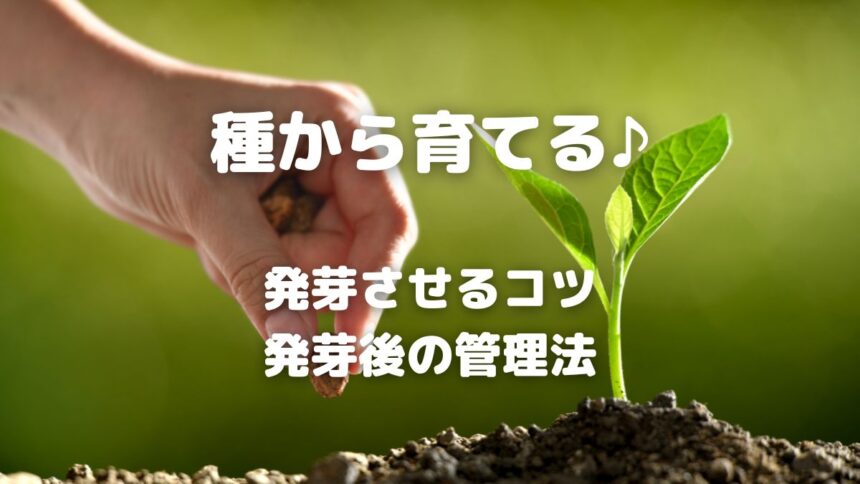種まきには、適切な「土」と「気温」がポイントになります
発芽に適した気温になってから、最適な土質の場所に植えることです
発芽した後には、徐々に「日当たり」よい場所へと移動させます
急激な環境変化は、まだ弱い苗にとってストレスです
いきなり強い日光に当たると、枯れてしまうこともあります
種まきの時期

種子が発芽するには「温かい気温」であることが基本的な条件です
そのため一般的には「春」か「秋」に種を蒔き、室内で管理します
【春に種まきするもの】
3~4月 トマト、ニラ、大麦、ゴボウ、ラベンダー
3~5月 パプリカ、コリアンダー、亜麻
4月~5月 マジョラム、バジル、ゴマ、綿花
4~6月 枝豆、大豆、カボチャ、ニンジン
5~6月 トウモロコシ、ズッキーニ
【夏に種まきするもの】
7~8月 ニンジン
8~9月 ゴボウ
【秋に種まきするもの】
9月 玉ねぎ
9月中旬~10月 マジョラム、コリアンダー、亜麻
10~11月 麦類、カラシナ
とはいえ毎年の気候は変動しますので、これらは目安に過ぎません
例えば秋に気温が上昇して虫が発生することがあり、遅めに種まきしたほうが良い年もあります
逆に、春に種まきしたのに、遅霜で枯れてしまう年もあります
ですから1週間おき、あるいは3~4日ずつ「数回に分けて種まき」したほうが失敗しません
あるいは生育の早さが異なる品種を混ぜて植えることで、よく育つ場合もあります
種まき道具

種まきに必要なのは「土」と「容器」だけです
とはいえ平たい容器に種を蒔いて、発芽してからポットに移植するのは大変
そのため小さな容器を使い、それぞれに 3 ~ 4 個の種をまくほうが失敗しません
【種まき容器】
防水性のあるものなら何でも、容器として使えます
例えば紙製の卵パックなら、一つずつ切り離して、そのまま植え替え可能です
個々の苗を植える時には、ヨーグルトのカップなどが使えます
種まき用のピートポットやピートペレットも便利です
苗の根は培地を通って土の中に直接伸びるので、楽に植え替えができます
ピートペレットやピートポットは、大きめの容器に入れて使うこともできます
【種まき用土】

鉱物でできた「バーミキュライト」は、軽く、多孔質で、保水力があります
価格も安いので人気の種まき用土です
保湿力を高めるために、ミズゴケと混ぜて使用されることもあります
市販の種まき用土は、通常「バーミキュライト」「ミズゴケ」「植物堆肥」などを混ぜたものです
堆肥や庭の土も使えますが、病原体や昆虫の卵が残っていることがあるので滅菌が必要です
滅菌するためには、浅い鍋に入れて低速オーブンで80℃くらいまで加熱します
土の温度は調理用の温度計で確認できます
植物性の堆肥や腐葉土も「種まき」や「苗の植え付け」に使えます

堆肥とは「堆積」してできる自然な「肥料」のこと腐葉土とは「腐った」「葉」が「土」に変わったもの。「堆肥」には養分が残っていますが、「腐葉土」には養分がほとんど残っていません。どちらも「有機物」が「微生物」によって分解されたものです。
堆肥と腐葉土の作り方は同じですが、熟成させる期間が異なります
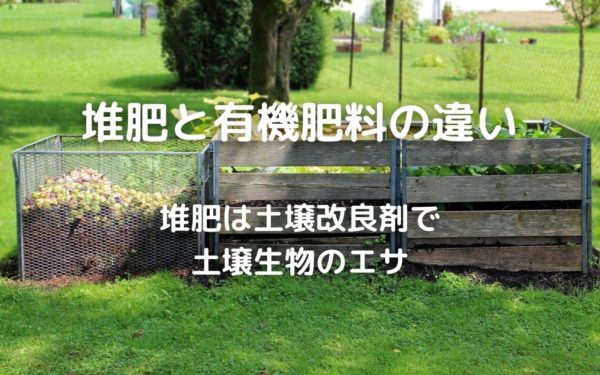
堆肥は土中に棲む「微生物のエサ」となるもので、植物の肥料ではありません。植物は堆肥そのものを直接、取り込むことができないからです。有機物が微生物によって分解されることで、植物が吸収できる「養分」に変わります。
堆肥や腐葉土を種まきに使う場合も、殺菌してから種を蒔きます
種まきのコツ

種子は暗所に保管しておくと発芽を早めることができます
そして種は多めにまいて、一斉に発芽させてから間引きます
一斉に発芽すると互いに協力して根が深く伸びるからです
樹木や多年草は、発芽にも、成長にも、とても時間がかかります
そのため慣れないうちは丈夫な一年草から始めると失敗しません
【水やり】
まずは種を蒔く前に、土を湿らせておきます
なぜなら、上から水をかけると種が流されてしまうからです
浅い容器に水を張り、容器ごと底から水を吸わせるようにすると湿らせることができます
自然栽培では「種まき」や「植え付け」直後に水やりしません
すると植物は、水を求めて根を伸ばそうとするからです
そのため、過度に水や肥料を与えないほうが、植物は強く育ちます
ですが「1週間以上」も雨が降らない時には水やり必要になります
根が張るまでは、ゆっくり生育します
けれど、しっかり根付いた後は元気に育っていきます

自然農法や自然栽培は「農薬や肥料を使わない」「自然に委ねる」栽培方法です。どちらも自然の「生態系」を活かすという考え方が基本にあります。ですから「植物」と「動物」との共生関係や食物連鎖がポイントです。
【ミニ温室】
水分を保つうえで効果的なのが、家庭にあるもので作れるミニ温室です
例えば、大きめの透明プラスチックボトルなら上半分を切って蓋にできます
透明な卵パックなら、数粒ずつ種を蒔き、そのまま蓋を閉めることができます

種まきから発芽までは適度な水分が必要ですが、ジメジメするとカビ菌が発生します
そのため発芽して苗が伸びてきたら、すぐに卵パックの蓋を外します
湿気がこもったままにすると病気や根腐れの原因となります
紙パックや卵の殻なら、そのまま土に埋められるので便利です

輪にしたワイヤーを数本ほど立て、上部に割り箸などを止めてラップで覆えばミニ温室にもできます
【間引き】
本葉が開いて競合しはじめたら、間引いて株間を広げます
先に伸びた芽を切り取って、後から出てきた芽を残すのがコツです
ゆっくり芽を出した種の方が丈夫に育つ傾向があります
さらに本葉が4~8枚になったら地面や鉢に移植できます
【日当たり】
移植して最初の数日間は、苗に直射日光が当たらないようにするのがコツです
とはいえ苗木は1日に少なくとも「 6 時間」は日が当たる必要があります
室内なら南または東向きの窓辺が最もよく育ちます
日当たりが悪い場合には、苗木の上15cmくらいの高さに40ワットの白色蛍光灯を設置します
定植前に成長しすぎると、発育が鈍くなり、収量が低下する傾向があります
そのため早めに定植することも大事です
野菜の種まき

野菜は一年で収穫するものなので、毎年、種から育てます
種から育てると無農薬栽培が可能です
低コストで、たくさん苗が作れることもメリットです
相性の良い野菜やハーブと一緒に栽培すると上手く育ちます
【トマト】
発芽適温は20~30℃、生育適温は15~25℃、種まき時期は3~4月
一緒に育てると良いのが「バジル」や「ニラ」です

トマトとバジルは一緒に料理しても栽培しても良い組み合わせ。近くに植えると、互いに味を良くして風味を高めます。「ニラ」や「バジル」をトマトと一緒に植えると病害虫を抑えられます。トマトの収穫後に栽培できるのが「ニンニク」。抗菌成分があり、強い香りで病害虫を防ぎ、モグラ除けにもなります。
【豆類】
枝豆・大豆の発芽適温は25~30℃、生育適温は20~25℃、種まき時期は4~6月
「早生」か「極早生」の枝豆なら4月下旬~6月上旬に種を蒔きます
豆類は「鳥」に食べられやすいので、夕方に種まきすると見つかりにくくなります
種まきした列のすぐ上に「紐」を張っておくのも鳥よけになります
まずは列の両端に支柱を立て、地面ぎりぎりに張った紐に沿って種をまきます
そして、まき終わったら紐の高さを15cmくらいに上げておきます
植え穴の周囲の草を刈り取り、種をまいた上に敷いておきます
こうすると、双葉の時期に周囲の草が目隠しになって鳥の被害が少なくなります
この頃になれば、種の上に張った紐を外しても大丈夫です
発芽しにくい場合は「燻炭」を種と同量くらいまきます
さらに緑肥として大麦の種を3~4月に蒔いておくと生育が良くなります
【人参】
発芽適温は15~25℃、生育適温は20℃、種まき時期は4~5月
ニンジンは発芽させるのが難しい野菜です
それは発芽する時に「光」を必要とするからです
とはいえ光が通るよう土を薄くかけると、今度は水分を保ちにくくなります
そのため、しっかり「土を押さえ」て種と土を密着させるのがコツです
まず種をまく場所は「溝を広め」にし「凹凸がないよう」均一にならします
水分を保ちやすい「雨の日の翌日」か「曇りの日の夕方」が種まきに適しています
種は5mm間隔くらいのばらまき、または3~4粒ずつ点々と蒔きます
ばらまきした場合は、1枚の本葉が出るたびに頻繁な間引きが必要です
ですから点々と少しずつ蒔いた方が間引きを少なくできます
ニンジンは「種を多めに蒔き」本葉が出てきたら間引きます
セリ科のニンジンは、生育初期に競い合うことでよく育つからです
覆う土は種の厚さの1~2倍くらい、種が隠れる程度に「薄く」土をかけるのがコツです
乾きやすい場所では、土を押さえてから「籾殻」を撒いて押さえておきます
それ以降の水やりは不要です
10日経っても発芽しない場合には、もう一度まき直します
【ゴボウ】
発芽適温、生育適温は20~25℃、種まき時期は3月~4月、8月~9月
溝の中央部分に、1か所に3粒ずつ、15cm間隔でまきます

ニンジンとゴボウは一緒に植えるとよく育ちます。生育適温がニンジンもゴボウも「15~20℃」と同じだからです。どちらも直根で根がまっすぐ深く伸びるので一緒に植えても競合しません。例えば春に種まきすると夏~秋に収穫できます。あるいは夏に種まきして雪の下から収穫すると甘いニンジンになります。
【パプリカ】
発芽適温は25~30℃、生育適温は15~30℃、種まき時期は3~5月
低温だと発芽しないので、充分に温かくなってから種まきします
ピーマン類は発芽させて苗に育てるまでの「温度管理」が難しい野菜です
特に大きくなるパプリカは「養分」と「水分」の管理も大変
そのため最初は苗を購入したほうが楽に栽培できます
種まき用土に「苦土石灰(一つまみ)」と「堆肥」を入れ、水やりして湿らせておきます
直径9cmの鉢なら「4粒」くらい種を蒔いて、薄く土をかけます
過湿を嫌いますが、乾燥にも注意が必要です
そして本葉3~4枚までに間引いて1本にします

パプリカは「豆類」と一緒に育てると、よく育ちます。土を肥沃にする豆類が、パプリカに十分な養分を提供するからです。互いに害虫を寄せ付けない組み合わせでもあります。
【カボチャ】
発芽適温は25~30℃、生育適温は17~20℃、種まき時期は4月~6月
寒さに弱い「日本カボチャ」は、4月下旬からポットに種まきします
地面に直まきせず、温かくなってから種をまき、ポットで苗を育ててから植え付けします
本葉が3~4枚になってから若い苗を植え付けすると、安定して実付きが良くなります
カボチャとトウモロコシは、一緒に植えると良い組み合わせです
連作障害がないので毎年同じ場所で栽培できます
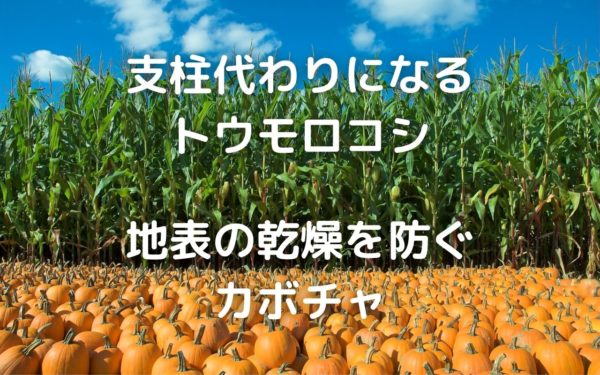
カボチャとトウモロコシは、一緒に育てると相性が良い組み合わせ。アメリカ先住民族が古くから行ってきた栽培方法です。トウモロコシを「東側」に植えると、カボチャは太陽に向かって伸びます。するとカボチャがトウモロコシの株元に絡みながらよく生育します。
トウモロコシの種まきは、カボチャを植え付けする「10日前」までに済ませておきます
これはカボチャよりトウモロコシを先に発芽させるためです
するとトウモロコシがカボチャの葉の陰にならず、よく育ちます
まず「東側」にトウモロコシの種をまきます
そしてトウモロコシが発芽してから「西側」にカボチャの苗2株を植えます
するとカボチャはトウモロコシの方へと伸びて、蔓を絡ませながら成長します
【トウモロコシ】
発芽適温・生育適温は25~30℃で、種まき時期は5月
酸性~中性で、水はけの良い、乾いた土で栽培します
花粉が風で運ばれるため、「10株以上」を「2列」にして植えると受粉しやすくなります
栽培スペースは「幅100cm×長さ200cm」くらい
まず中央に2列、列の間を30cmあけて7か所ずつ、1か所に2~3粒ずつ点まきします
トウモロコシの種は、尖ったほうを下にして植えると発芽率が良くなります
そして鳥に食べられないよう、土をかぶせてから刈り取った草を敷いておきます
豆類と一緒に育てると、マメ科に付く根粒菌の働きで土が肥沃になってよく育ちます
枝豆や大豆がトウモロコシの陰になり、種や発芽した双葉を鳥に食べられにくくなるメリットもあります
1週間ずらして2回に分けて種まきすると収穫期間が長くなります
例えば1列目は5月上旬、2列目は5月中旬に
【ズッキーニ】
発芽適温は25~30℃、生育適温は15~20℃、種まき時期は5~6月
1か所に3~4粒ずつ「方向を揃えて」まきます
そして土で覆った上には刈り取った草を敷くだけで、水やりは不要です
ズッキーニは、やや「西寄りに配置」すると最終的には中央になります
それは蔓が東へ向かって伸びるからです
【玉ねぎ】
発芽適温は15~20℃、生育適温は15~25℃、種まき時期は9月
まずは時期を逃さず植え付けすることが大事です
1列に「5mm」間隔で、10cm離して2列に、点々と種をまきます
そして厚さ5mmの「土」をかけ、「もみ殻」を上にまき、足で踏んで押さえます
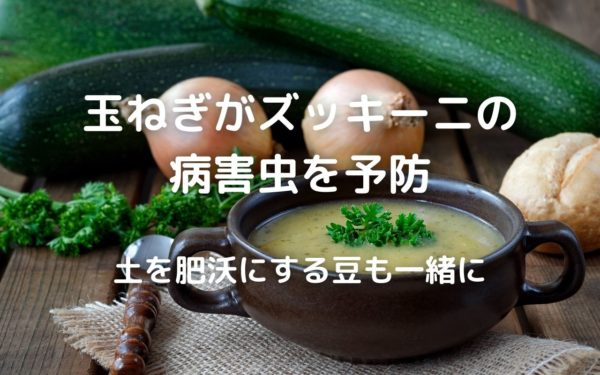
玉ねぎの収穫後に植えると丁度いいのがズッキーニ。栽培する時期が、ちょうどリレーのように続けられるからです。3月から「土の準備」をして「秋」に玉ねぎを植えます。ズッキーニも玉ねぎも「肥沃な土」を好む野菜。玉ねぎの収穫後にズッキーニを栽培すると、余った肥料分が吸収されます。
【麦類】
発芽適温は小麦が25℃で大麦が10~15℃、生育適温は小麦で25℃で大麦が20℃
種まき時期は最低温度3~5℃の10~11月です
早く種まきすると、年内に大きくなり、冬の寒さで枯れてしまいます
遅く種まきすると、翌春に分げつが遅れて収量が減ります
麦の種は1か所に「5~10粒」まきます
よく肥えた土なら10粒、土作りの途中なら5粒です
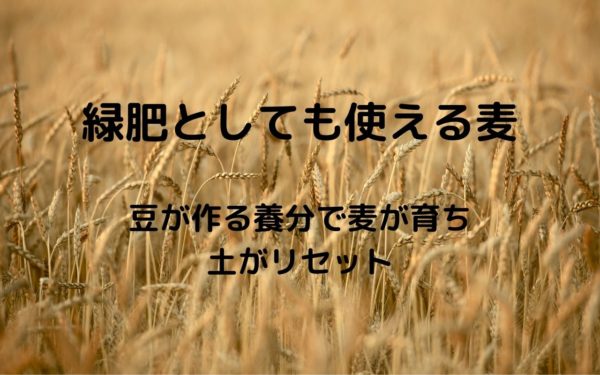
豆類と麦類は、交互に植えると良く育ちます。麦類は余分な肥料分を吸い取るので、枝豆の蔓ボケを防ぐからです。連作障害も起きにくくなります。麦類は、枝豆に付く害虫を防ぐ働きもします。豆類に付くアブラムシと麦類に付くアブラムシは別の種類だからです。
ハーブの種まき

ゆっくり育つのは、どの多年草にも共通した性質です
季節にもよりますが、芽が出るまでに2~4週間ほどかかります
そのため芽が出るまで、土が乾かないよう、ジメジメしないよう、注意が必要です
発芽する前も後も、上から水やりせずに、鉢底から水を吸わせる方が芽を傷めません
そして受け皿に溜まった水は捨て、土が湿りすぎないようにします
【ラベンダー】
発芽適温・生育適温は15~20℃、種まき時期は3~4月
芽が出るまでに低温の期間があることも大事で、2週間くらいで発芽します
ラベンダーは買ってきた苗を植えた方が簡単に育ちます
種は発芽しにくく、苗に育てるまでの管理が難しいからです
とはいえ種から育てられないわけではありません

ラベンダーは目的に応じて品種を選べるハーブ。原産地や品種改良によって、多くの種類があるからです。品種によって活用方法も違ってきます。庭に植えて観賞するなら、花が美しく、長く咲く品種が最適。ポプリやドライフラワーにするなら、香りが良い品種を選びたい。
【コリアンダー】
発芽適温は20~25℃、生育適温は18~25℃、種まき時期は3~5月または9~10月
気温が20℃くらいあると発芽します
柔らかな葉を収穫するのなら3~5月の春に、種を収穫するなら9~10月の秋にします
夏に種まきすると虫が付きやすくなります
秋に種をまいて冬の間に室内で栽培すると、気温が高くなる頃に花が咲き始めます
種は「深めのプランター」に直接まき、そのまま「植え替えしない」で育てます
これは、コリアンダーの根がまっすぐ下へ伸びる性質があるからです
そのため種をまく「鉢」は深さ18cmくらいのものを使います
生育の良いものだけ残しながら間引きますが、間引いた苗も料理に使えます
そして最終的には間隔が5cmくらいにして育てます
あまり大きくならないので、プランターでも育てやすいハーブです

英語圏での呼び方が「コリアンダー」。別名では「チャイニーズ・パセリ」「コエンドロ」タイでは「パクチー」、中国では「シャンツァイ(香菜)」です。日本では「カメムシソウ」とも呼ばれています。独特な臭いが苦手な人とクセになる人と、好き嫌いがハッキリ分かれるハーブです。
【マジョラム】
発芽適温は15~30℃、生育適温は10~20℃、種まき時期は4~5月か9~10月
暖地の場合は春まきのほうが育てやすく、「屋外で冬越し」させると強く育ちます

オレガノはマジョラムの一種で、同じ仲間のハーブ。マジョラムは大きく3種類に分けられ、最も味と香りが強いのがオレガノです。それぞれ「原産地」や「使われる料理」が異なり、呼び名が様々にあります。
【バジル】
発芽適温は20~25℃、生育適温は15~30℃、種まき時期は4月~5月
温かくなってからでないと芽が出ないので、初夏に種まきします
種からでも簡単に育ちます
【ゴマ】
発芽適温は25℃、生育適温は25~35℃、種まき時期は4~6月
ゴマは温かくないと育たないので「種まき時期」が大事
そのため充分に気温が上がってから種まきします
地温が「20℃」以上、平均気温「16℃」が適期です
目安は「藤の花が満開」になる頃あるいは「小麦の穂が出てから」
気温10℃くらいでも発芽しますが、時間がかかり、生育も良くありません
種まきが遅れると生育量が少なくなります
ゴマは、直播より温かい場所で「苗を育ててから定植」するほうが簡単に育てられます
発芽直後は草と見分けがつきにくいからです
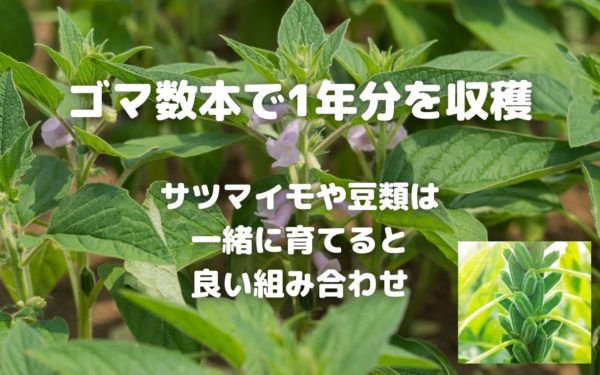
ゴマは比較的生育が早く、手がかかりません。数本で充分な量が収穫できます。土質も選ばず、極端な酸性土でなければ、どこでも栽培できます。「風通し良く」してジメジメさせないことがポイントです。ゴマは「暑さに強く」夏の日差しが大好き。雨季に発芽して根を伸ばし、乾季の日照りで大きく育ちます。
【カラシナ】
発芽適温は20~25℃、生育適温は15~20℃、種まき時期は10~12月
カラシナはカメムシを引き寄せるので、玄関やベランダの外に植えると、室内への侵入を防げます
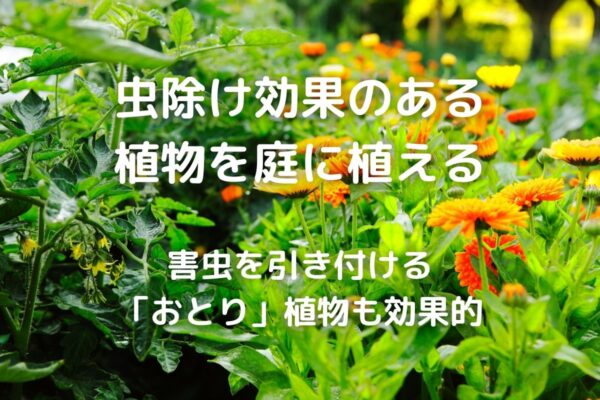
庭や菜園に植えた植物によって、害虫を防ぐことができます。虫によって、植物の好き嫌いがあるからです。例えば、ハーブの強い香りを嫌う虫は多くいます。逆に虫が好む植物を「おとり」として植え、他の植物を守る方法もあります。
繊維植物の種まき

亜麻や綿花は可愛らしい植物です
さらには繊維を採ってリネンやコットンの布に織る楽しみも味わえます
冷涼な気候に向いているのが亜麻、温暖な気候に向いているのが綿花です
【亜麻】
発芽適温は20℃、生育適温は11~18℃、種まき時期は3~5月、9~10月
亜麻は寒さに強いですが、暑さや湿気には弱い植物です
日本では北海道のみが栽培適地と言われます

昔の主婦は「糸紡ぎ」や「機織り」を家事として日常的に行っていました。現在でも、趣味として糸紡ぎや機織りをする人がいます。黙々と手を動かすだけの単純作業をしている時間は、まるで瞑想のようです。
【綿花】
発芽適温は15~20℃、生育適温は25~35℃、種まき時期は4月
ポットで育て、間引いて1本にした苗を5月に定植します
地面に直接まく場合は5月に種まきします
温かくならないと発芽しないので、寒い場所ならマルチなどの保護が必要です
まずは綿毛に包まれた種は水に入れて少しもみ、水を含ませて一晩そのまま浸けておきます
それから1か所に2~3粒の種をまき、本葉が出たら間引いて1本にします
水はけの良い肥沃な土がワタの栽培に適しています
そのため種まきの1週間以上前に元肥を土に混ぜておきます
元肥は、油かすと苦土石灰を1㎡あたり一握りほど
酸性度を嫌うので、定期的に苦土石灰や草木灰を与えると病害虫に強くなります
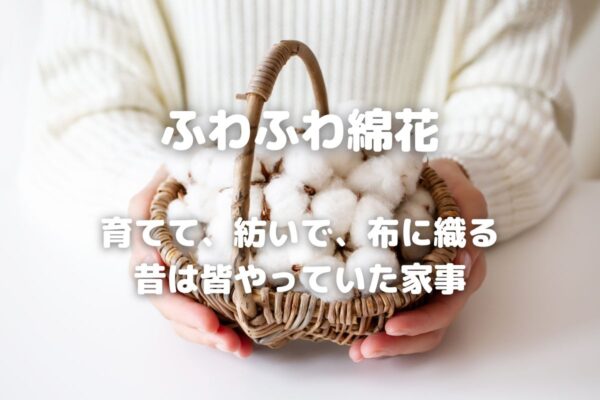
綿はワタという植物の実から採った毛を糸にして布に織ったもの。昔は、どこの家庭でも衣服を自分で作っていました。現在では糸紡ぎや機織りは「趣味」のひとつ。ガーデニングの延長で綿花を育て、布に織るのも面白い試みです。時間と手間はかかりますが、難しい作業ではありません。
当ブログの記事を整理してアマゾンKindleの電子書籍と紙の書籍で出版しています
Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください