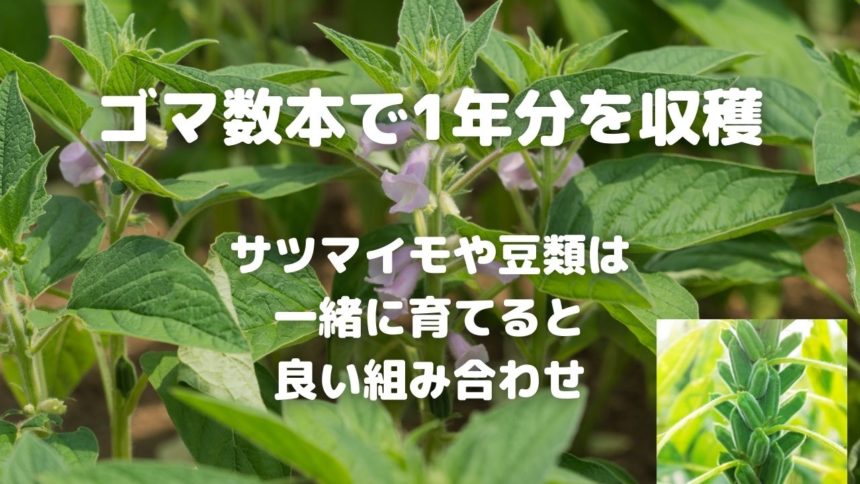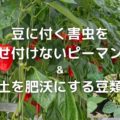ゴマ栽培を始めるのは、十分に暖かくなってから
なぜなら霜に弱く、暑さには強いからです
そして日当たりの良い場所で、風通し良くして育てるのがポイントです
春に種まきすると、雨期に発芽して根を伸ばし、真夏の日差しで大きく育ちます
自家受粉するので、1本だけ植えても収穫できます
ゴマのコンパニオンプランツ

ゴマのコンパニオンプランツは「サツマイモ」「麦類」「枝豆」「落花生」
そして一所に植えると良いのは、サツマイモ、枝豆、落花生です
麦類は、ゴマと交互に植えると、連作障害を減らすことができます
逆に、キャベツとは、相性が悪い組み合わせです
【ゴマとサツマイモ栽培】
ゴマとサツマイモは同じ環境を好むので、混植に向いています
さらに生長したゴマの株元をサツマイモの葉が覆うのも良い効果となります
まず中央にサツマイモを植え、両サイドにゴマを植えます
ゴマは2本くらいに間引いてから、サツマイモとは50cmくらい離して
なぜなら間隔を広くすることで、サツマイモにもよく日が当たるからです
【ゴマと豆類の栽培】
中央に枝豆や落花生を植えておき、両側にゴマを植えてもよく育ちます
枝豆は30cm間隔、ゴマは30~50cm間隔で
落花生の種まき、植え付けは5~6月が適期です
ゴマは根が深いので倒れにくいですが、強い風が当たると枝が裂けやすくなります
そのため風上には「風除け」になるものを植えると防げます
そこで丁度よいのが、トウモロコシです
まず通路として50cm以上を開け、100cm幅にトウモロコシを50cm間隔で植えます
あるいはトウモロコシの間に枝豆を植えてもOK
トウモロコシは、カボチャとも相性が良い組み合わせです
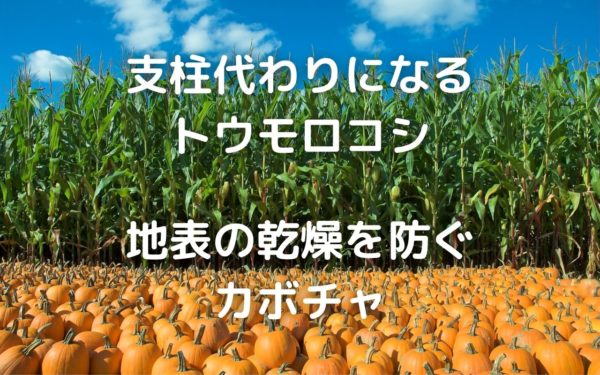
カボチャとトウモロコシは、一緒に育てると相性が良い組み合わせ。アメリカ先住民族が古くから行ってきた栽培方法です。トウモロコシを「東側」に植えると、カボチャは太陽に向かって伸びます。するとカボチャがトウモロコシの株元に絡みながらよく生育します。
【ゴマと麦類の栽培】
ゴマと麦類を交互に育てると、連作障害を減らすことができます
そのためゴマの収穫が終わった秋に、麦の種まきをしておきます
そして翌春の5月に麦を収穫したら、その切り株の間にゴマを定植できます
例えば大麦の種なら50cm間隔で、120cm離して2列に蒔きます
大麦の若葉は「猫草」として使われるものです
麦類は、豆類と交互に栽培しても良い組み合わせです
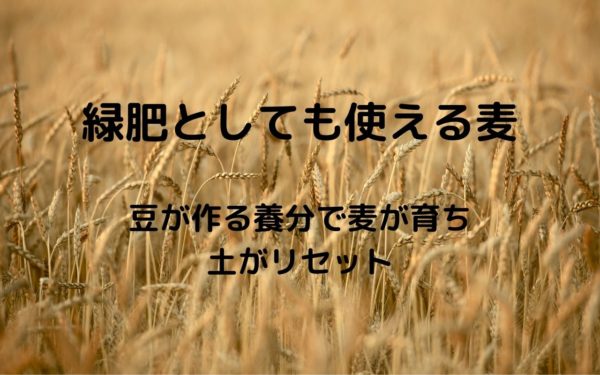
豆類と麦類は、交互に植えると良く育ちます。麦類は余分な肥料分を吸い取るので、枝豆の蔓ボケを防ぐからです。連作障害も起きにくくなります。麦類は、枝豆に付く害虫を防ぐ働きもします。豆類に付くアブラムシと麦類に付くアブラムシは別の種類だからです。
ゴマ栽培の方法

ゴマ栽培は意外と簡単
なぜなら生育が早く、同じ場所で連作でき、土質も選ばないからです
例えば、極端な酸性土でなければ、どこでもゴマ栽培できます
そのため、あまり手がかからず、数本で充分な量が収穫できます
●胡麻(ゴマ科ゴマ属の一年草)
発芽の適温は25℃くらい、生育適温は25~35℃です
原産地は東インドからエジプトで、アフリカ大陸で野生種が多く自生しています
●ゴマ栽培カレンダー

ゴマは、地面に種まきするよりも、温かい場所で「苗を育ててから定植」するほうが簡単
なぜなら発芽直後は草と見分けがつきにくいからです
そして草が生い茂ると草負けして育たないので、草刈りが欠かせません
【ゴマの種まき時期】
ゴマは温かくないと育たないので「種まき時期」が大事です
まずは充分に気温が上がってから種まきします
例えば地温が「20℃」以上、平均気温「16℃」が適期です
ゴマの種まき適期の目安は「藤の花が満開」になる頃
あるいは「小麦の穂が出てから」
気温10℃くらいでも発芽しますが、時間がかかり、生育も良くありません
そして種まきが遅れると、生育量が少なくなります
金ゴマは香りが良くて使いやすい品種です
黒ゴマは香りが芳ばしい品種
白ゴマは油脂が多くまろやかな品種です
ごまぞうはゴマリグナンを多く含む新品種です
【ゴマの種の蒔き方】
土は「1週間以上前」から用意しておき、定植の「2週間前」に種をまきます
まず「培養土8:畑の土2:籾殻燻炭1」の割合で混ぜたものを準備
水を加えて混ぜ、「握ると固まり」「突くと崩れる」程度の水分量にします
次にポットに土を詰め、上から押さえて平らにしておきます
そして土の真ん中を軽くくぼませて「4~5粒」くらい種をまきます
最後に土を「5mm」くらいの厚さでかけ、しっかり押さえます
さらに薄く「籾殻燻炭」をかけておくと、乾燥を防ぎ、地温を上げる効果もあります
ポットごと「新聞紙」などで包み、その上から十分に水やりします
そのまま温かい場所に置き、新聞紙は「2日後の朝」には必ず取り除きます
包んだままにしておくと、カビが生えたりします
●地面に直播きする場合
まず種まきする場所の「草」を地際で刈り取ります
表面の「土」を5mmくらい削り、鎌の先を土に差し込んで草の根を切っておきます
そして種をまく場所は土を押さえて平らにならしておきます
1か所に「5~6粒」ずつ、株間は「30~50cm」あけて点まきします
種が小さいので、かける土は薄く「5mm」くらいです
地表「1~2cm」部分の土には草の種が多いので、取り除いて、その下の土を上からかけます
風で飛ばされることがあるので、しっかり押さえておきます
最後に「刈り取った草」を薄く敷いて乾燥を防ぎます
ゴマの植え付け
ゴマ定植の適期は「藤の花が満開」になった時期、あるいは「本葉3~4枚」の頃
本葉4~5枚になった頃に間引いてから定植してもOKです
ですが定植が遅れると根付きが悪くなります
ゴマ栽培の場所は「日当たり良い」「水はけの良い土」で「やや乾燥気味」が最適です
【土の準備】
ゴマ栽培に適した土質は、ペーハー6.0~6.5くらいの「酸性土」です
ゴマは「肥沃な土」に植え、「肥料は与えず」育てるのがコツ
なぜなら養分が多すぎると倒れやすく、葉が茂って実が付きにくくなるからです
例えば、トマトなどの果菜類やアブラナ科の野菜が育った土なら無肥料で育ちます
土が痩せている場合のみ、定植する1カ月前に準備しておきます
1m四方の土に「完熟堆肥(1~2リットル)」「籾殻燻炭(1~2リットル)」を混ぜておきます
堆肥は完全に熟したものでないと根を傷める原因となります
籾殻燻炭は焼きすぎていないものが良質です
土となじむよう表面5cmくらいを軽く耕しておけば、ゴマ栽培の準備はOK
【ゴマの定植】
まず定植する前日の「夕方」にたっぷり水やりします
定植する日は「3時間前」から苗の底を水に浸して吸水させます
草に覆われると育ちにくいので、周囲の草は刈り取って地面に敷いておきます
ですが間隔が30cm以下だと株元の草刈りがしにくくなります
そのため「株間50cm」くらい開けて定植します
5月下旬~6月中旬「本葉4~5枚」になったら1~2本に間引きます
葉が混みすぎている場合には、苗を育てている期間でも間引きます
株間30cmなら1本だけ残し、株間50cmなら2本を残して、他はハサミで切り取ります
間引いた後も、周囲の草を刈り取って地面に敷いておきます
7~8月、初期の生育が悪い場合は「米ぬか」をプラスすると効果的
株の周囲に一握りくらい、草マルチの上からまきます
その後は草マルチを重ねていきます
ゴマの収穫時期
草丈が高く伸びると、下から順に花が咲き、実も下から順に熟します
そして「下のさや」が弾け始めたら収穫時期です
遅れるとさやからゴマが落ちて収量が減り、風味も落ちます
9月になり、下側のさやが枯れて2~3個開き始めたら、茎ごと刈り取ります
【ゴマの収穫方法】
種をこぼさないよう「早めに刈り取る」のがコツです
刈り取りは「朝方」にすると、ゴマを落とさずに済みます
揺れないようハサミで静かに茎を切り、その場でシートや袋にゴマを受けます
刈り取った後は、9~10月に「雨に当たらず」「日の当たる」場所で追熟します
【ゴマ収穫後の処理】
10月に上のさやが弾けるようになったら「脱穀」です
まず「天気の良い午後」に容器で受けながら頭を下にして振ります
容器は、結露しにくい「紙袋」「ダンボール」「ゴザ」「布バッグ」で
さやをつぶし、残ったゴマを取り出し、葉などのゴミは「ふるい」にかけて取り除きます
細かなゴミは息を吹きかけて飛ばします
取り出したゴマは、天気の良い日に水洗い
気泡が付いて多くのゴマが浮き上がりますが、全て残します
ゆっくり別の容器へ移しながら、底に残った石や砂を取り除きます
何度か繰り返してから寒冷紗などに広げて「天日干し」します
この時に、ネットなどで覆っておくと、風で飛ぶのを防げます
【ゴマの保存法】
完全に乾いてからビンなどに入れて保存
食用にすると共に翌年の種としても使えます
種の寿命は3~5年くらいです
ゴマは数本を育てるだけで1年分を収穫できます
たくさん収穫できたら、ゴマ豆腐を作ってみては
精進料理の華となるのがゴマ豆腐です

ゴマ豆腐は、豆腐とは作り方や材料が違います。豆腐は「大豆」を絞って「にがり」で固め、ゴマ豆腐は「ゴマ」を練って「葛粉」で固めたもの。それぞれ材料を変えてアレンジできます。
ゴマなどの健康野菜を中心に解説しているのがこの一冊です
スイカ、オクラ、ゴマ、トウガン、食用ホオズキ、芽キャベツ、ニンニク、シュンギク、菜の花、セロリ、アスパラ、ラッカセイ、モロヘヤ、ゴーヤ、ショウガとウコン、ヘチマ、エゴマ、ニラ、小豆、ブロッコリとカリフラワー、野沢菜、コンニャク、ヤーコン、ゴボウ
24種類の野菜の育て方が書かれています
当ブログの記事を整理して、アマゾンKindleの電子書籍と紙の書籍で出版しています
Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください