庭に生える雑草を抑えるには、除草剤をまいてしまうのが簡単です
とはいえ家庭菜園を作ったり、ペットが遊ぶ庭に、除草剤は使いたくありません
そんな場合に効果的なのが、通路などにレンガや砂利を敷く方法です
コンクリートやモルタルを使わずに施工できる方法もあります
庭に生える雑草を砂利で抑える方法

庭に生える雑草を抑えるうえで、最も簡単なのが砂利を敷くことです
なぜなら砂利は地面に敷くだけですし、形を自由にできます
例えば狭い場所でも、曲がりくねった場所でも、調整可能です
【砂利のデメリット】
砂利のデメリットは主に3つあります
- 隙間から雑草が生えてくる
- 砂利が地面に埋まってしまう
- 落ち葉などを掃除しにくい
例えば完全に雑草を防ぐには、地面を「モルタル」や「漆喰」で固める必要があります
モルタルなどを使わない場合は「ビニールシート」を敷いておきます
シートを敷いておけば、砂利が地面に埋まるのも防げます
とはいえシートは数年で劣化するため、砂利を外して敷きなおす必要があります
そして砂利は「頻繁に歩く場所」や、落ち葉が多い「落葉樹の下」には不向きです
上を歩いたり、箒で掃いたりすると、砂利が動いて減っていくからです
【庭に敷くと効果的な砂利】
南向きや西向きの地面に「溶岩砂利」を敷くと、真夏の暑さを和らげることができます
なぜなら「打ち水効果」が非常に高いからです
そして気泡が多くゴツゴツしているので、通気性が良く、保水力もあります
泥棒に侵入されやすい通路に最適なのが「防犯砂利」です
なぜなら歩くと高い音が鳴るので、侵入者に早く気づけます
- 1階の窓
- ベランダの外
- 玄関アプローチ
こういった部分に敷いておくと、泥棒などは音を嫌って侵入してきません
砂利の必要量は、4cm厚さに敷く場合で「1平方メートル当たり40リットル」が目安です
多めに注文しておくと、減ってきたときに補充できます
特に人が歩く場所に砂利を敷いた場合、数年後には減った分の砂利を足す必要が出てきます
庭に生える雑草をレンガで抑える方法

庭に生える雑草を抑え、通路にも使えるのがレンガです
どんな庭にも合わせやすく、1個が小さいので女性でも持ち運びできます
大きさが一定なので、綺麗に並べるのも簡単です
庭木や植物を植えてある場所を避けながら、レンガの小道を作ることができます
地面にレンガを敷く場合は「砂」で固定しておく方法が簡単
乾いた砂は微調整しながら作業できるからです
後からレイアウト変更などできるのも砂のメリットです
モルタルを使うと、乾く前に修正しないと固まってしまいます
【レンガのサイズ】
レンガの標準サイズは「21×10×6cm」
長さを半分にしたのが「半マス」
厚みを半分にしたのが「半ペン」と呼ばれます
アンティークレンガは、大きさや形が不ぞろいです
敷き方が難しく、価格も高いですが、部分的に使うと良い感じに仕上がります
【レンガ道のレイアウト】
レンガ道のレイアウトによって、空間に広がりを感じさせることができます
- 小道を「S字状」にすると奥行を感じさせて広く見える
- 歩く方向に対してレンガを「横」に並べると、広がりを感じさせる
- 歩く方向に対してレンガを「縦」に並べると奥行を感じさせる
まずは置いてみることで、必要なレンガの「個数」を確認できます
もし足りなければ「小道の幅」や「隙間の間隔」を変えて調整が可能です
そしてレンガの置き方が決まったら、その「外側」にレンガを置いくと目印にできます
【地面の整地】
まず小道部分の地面は「15cm」くらい掘って平らにならしておきます
レンガの厚み分6cmと、底に5cm厚さの「砕石」と4cm厚さの「砂」を敷くためです
砕石と砂を敷くことで、レンガが地面に埋まっていくのを防げます
薄く土を掘る時に便利なのが「ジョレン」
刃先が平らで短いクワで、深く掘りすぎず、平らにならせます
柄の部分が長いと楽に作業ができます
シンプルなジョレンは、植物を植えた後に、土を根元に寄せる時などにも使えます
地面の整地にも使える便利な道具です
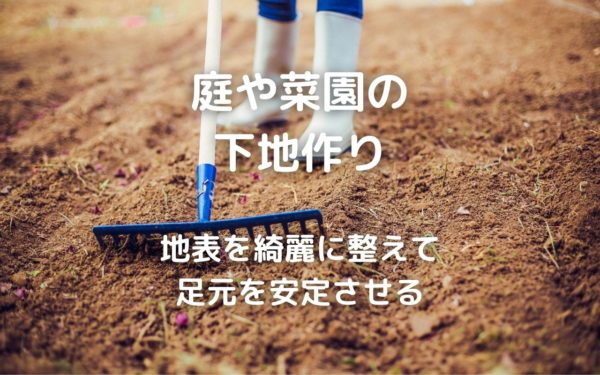
庭の地面は、まず平らにならして「整地」する必要があります。そのままでは表面が凸凹していたり、傾いていたりするからです。例えば、雑草を抜くと地面が凹んでしまいます。地中には、石やゴミが埋まっている場合もあります。ウッドデッキ、椅子、テーブルなどを置く場所なら「水平」にすることも大事です。
【砕石と砂を敷く】
まず「砕石」を敷いてから、その上に「砂」を敷きます
こうすることでレンガが地面に埋まるのを防げるからです
<5cmの厚みで敷く場合に必要な「砕石」の量の目安>
- 1平方メートル当たり100リットル
- 75~90㎏
砕石を敷いたら上に「板」を乗せ、足で踏み固めて平らにします
砕石の上に砂を敷き、同様にして平らにしておきます
<4cmの厚みで敷く場合に必要な「砂」の量の目安>
- 1平方メートル当たり80リットル
- 63~72㎏
砂の上にレンガを乗せて配置を確定します
【レンガを敷いて砂で固定する】
仮置きしたとおりにレンガを戻し、小道に敷いていきます
レンガが浮いている部分は「ゴムハンマー」で叩くと平らにできます
全てのレンガが敷けたら、レンガの上から「砂」をまきます
それから「ホウキ」で掃くと、レンガとレンガの間に砂が入って固定されます
最後にジョーロで水をまき、砂を落ち着かせたら完成です
庭に生える雑草を敷石で抑える方法

広いスペースで庭の雑草を抑えるのに効果的なのが、大きな敷石です
例えば、テーブルと椅子を置く場所など
落ち葉を掃き集めやすいので、落葉樹の下の涼しい木陰に最適です
同じサイズに切りそろえてあるので、綺麗に並べられます
一枚が大きいので、早く敷けることもメリットです
デメリットは重たいことで、建物の際などでの微調整もできません
とはいえ平たく大きいので地面に置くだけでも安定します
建物の際など、敷石が納まらない部分は「砂利」で埋めるのが簡単です
敷石をカットすることも可能ですが、複雑な形や細かいカットは無理
直線的に切って敷石を小さくするだけの加工なら可能です
カットしたい線上に「タガネ」を打ち、ハンマーでたたくと割れます
タガネは彫刻などに使う「ノミ」で代用できます
ステップストーンには形、大きさ、色、素材、豊富な種類があります
他にも、昔ながらの「たたき」で地面を固める方法もあります

自然素材で作った庭は、解体して作り直したり、土に埋めたりできます。庭づくりは一度では完成しないので、後から作り直せるほうが便利です。例えば、年齢や家族構成の変化に応じて庭での過ごし方も変わります。自分の好みだって変化します。そのため自然素材で作っておけば、後で解体して再利用することも可能です。
庭に生える雑草を活かす方法
庭の雑草は、そのまま生かせる場合もあります
例えば背の低い雑草なら、グランドカバーとして使えます

小さな雑草は、抜かずに残すとグランドカバーとして活かせます。背が高くなる草だけ抜いていけばいいので簡単。そして地面を草が覆っていると、他の雑草は生えなくなっていきます。雑草は、その場所に適応しているので手間も要りません。勝手に増えて拡がり、しかも地表の乾燥を防いでくれます。
花壇に植えてもいいような、かわいい雑草もあります
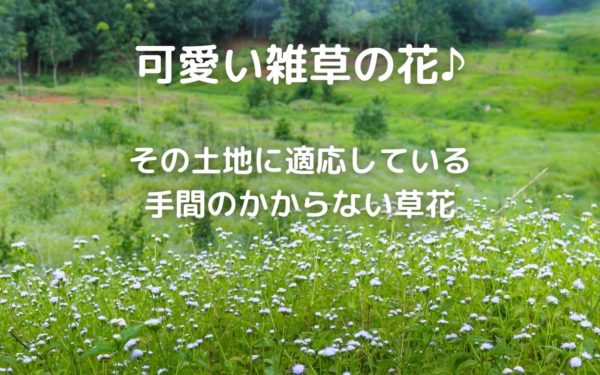
かわいい雑草は、抜かずに庭に活かすと手間がかかりません。なぜなら自然と生えてくる草は、その場所の土質や気候に適応しているからです。雑草とはいえ、もとは観賞用として持ち込まれたものもあります。あるいは園芸用の植物が繁殖して、雑草化していることもあります。
当ブログの記事を整理してアマゾンKindleの電子書籍と紙の本で出版しています
Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください

















