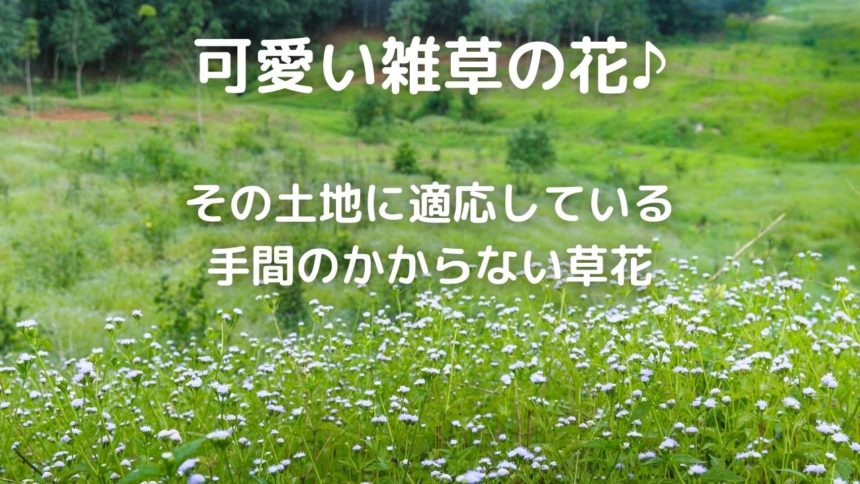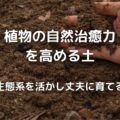かわいい雑草は、抜かずに庭に活かすと手間がかかりません
なぜなら自然と生えてくる草は、その場所の土質や気候に適応しているからです
雑草とはいえ、もとは観賞用として持ち込まれたものもあります
あるいは園芸用の植物が繁殖して、雑草化していることもあります
そして市販されている花も、探せば近所の路地や河原に自生しているかもしれません
かわいい雑草の開花時期

まずは雑草の開花時期に、生えている場所や葉の形を確認
そうすれば、花が咲いていない時期でも抜かずに
例えば「カンゾウ」は、葉だけだと雑草にしか見えません
ところが夏になると、ユリのような花が咲き、市販もされているほど
カンゾウの苗を買ってきて庭に植えたら、近所の河原に生えていた、という話もあります
可愛い花が咲く雑草には以下のようなものがあります
草丈の低い草なら、バラなどの足元を覆うグランドカバーとしても活かせます
●一年草
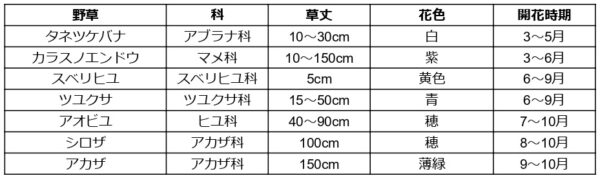
●多年草

早春に咲くかわいい雑草

早春に咲くのが「オオイヌノフグリ」「スミレ」「タネツケバナ」「コオニタビラコ」
まだ肌寒い日が残る、花の少ない時期に開花する貴重な草です
とはいえ夏になると葉だけになるので、うっかり刈り取ってしまいがち
かわいい雑草なので、残しておくと毎年ちゃんと咲いてくれます
【オオイヌノフグリ】

2~5月ころに咲いている、草丈10~20cmの雑草で、青い花が綺麗
道端や畑の畦道など、湿った土地に生えるかわいい雑草です
オオバコ科クワガタソウ属の越年草で、秋に発芽して冬に育ちます
そのため雪が積もらない地域なら、冬に緑の葉を伸ばしています
そして春の終わりには枯れて、夏は種子で過ごします
1~2cmの卵型で、ふちがギザギザした葉の形を覚えておくと、抜かずに済みます
【スミレ】

3~5月に紫色の花が咲き、草丈は5~12cmほど
平地から山間部まで生え、寒さにも暑さにも強い草です
根元から、先端が丸みのある細長い葉がたくさん出ます
パンジーやビオラなど、園芸品種が雑草化していることもあります
【タネツケバナ】

3~5月に白い小さな花が開花し、草丈は10~30cm
アブラナ科の越年草または一年草です
水田に群生しているような草で、水に浸かって生えていることもあります
茎の両側に小さな葉が左右対称について、クレソンに似ています
アイヌ料理では、鮭料理の香辛料として使われます
【コオニタビラコ】

3~5月に黄色い花が咲き、草丈は10cmくらい
キク科の越年草で、花が終わると丸い実が膨らみます
湿地を好む草で、田んぼの畦道などに生えています
細長い茎の両側に丸みのある葉が出ます

これは「仏の座」と呼ばれる春の七草のひとつで、市販もされています
ところが紫色の花が咲く「ホトケノザ」のほうは有毒で食べられません
【ナズナ】

2~6月に開花し、草丈は10~50cmくらい
アブラナ科ナズナ属
ぺんぺん草とも呼ばれます
株元の葉は大きく切れ込みがあり、大根の葉に似ています
春の七草のひとつで、1月7日に七草粥として食べます
若葉には鉄分などのミネラルが豊富に含まれます
そのため七草粥を作って食べると健康でいられると言われます
初夏に咲くかわいい雑草

春バラが咲き終わった頃に咲いてくれる雑草があると、庭が寂しくなりません
例えば、周囲の草を刈り取ると、雑草も綺麗に見えます
そして背の高い草なら、切り花にして飾ることもできます
【カラスノエンドウ】

3~6月スイートピーに似た花が咲き、草丈は10~150cm
マメ科ソラマメ属の越年草で、ヤハズエンドウとも呼ばれます
花が終わると黒いサヤができ、中の豆は食べられます
つる性ですが、直立して伸び、こじんまりしています
楕円形の葉が左右対称について、先端から巻きヒゲが出ています
【ハルジオン】

3~7月に白い花が咲き、草丈は30~80cm
キク科ヨモギ属
道端や空き地でも、よく見かける花です
ヒメジョオンより花びらが細く、秋になると花が咲かなくなります
【クリムソンクローバー】

マメ科の多年草で、草丈は20~60cm
4~6月に花が咲きます
赤い花が目を引く草です
ヨーロッパから西アジア原産で、暑さに弱いため日本では夏に枯れてしまいます
日当たりと風通しの良い場所で、水はけの良い土に植えるとよく育ちます
根づけば乾燥に強い草です
肥料は必要なく、咲いた花を切って減らすと、長く花が咲き続けます
【ユキノシタ】

ユキノシタ科の多年草で、草丈は20~50cm
5~7月に白い花が咲く、ロックガーデンに似合う花です
もともと岩場や石垣に自生する山野草
低く湿った谷川沿いとか半日陰に生えています
そのため日当たりの悪い場所でも育ち、常緑なので冬も緑の葉が残っています
真夏も咲いているかわいい雑草

バラは春と秋に咲き、真夏になると花が少なくなります
そんな時期をカバーしてくれる、かわいい雑草があると楽です
なぜなら真夏の炎天下に水やりなどしなくても、雑草は元気に育つからです
【アカツメクサ】

マメ科の多年草で、草丈は20~80cm
4~8月にピンクの花が咲きます
「ムラサキツメクサ」「赤クローバー」とも呼ばれます
葉が丸いシロツメクサとは違い、アカツメクサの葉は細い形の三つ葉
そして草丈も、シロツメクサより高くなります
【トキワツユクサ】

ツユクサ科の多年草で、草丈は50cmくらい
5~8月の初夏に、三角形の白い花を咲かせます
湿り気のある場所を好み、日陰や水辺に生えます
南米原産で、観賞用として持ち込まれてから野性化しています
【ヒメジョオン】

5~10月に白い花が咲き、草丈は30~50cm
キク科ヨモギ属
ハルジオンとよく似ていますが、開花期が異なります
秋まで咲いているのがヒメジョオンです
茎に空洞がなく、葉が外向きに開いて上のほうにあるので、根元がスッキリしています
【シャジクソウ】

6~8月に紫色の花が咲き、草丈は15~50cm
マメ科シャジクソウ属の多年草
クローバーの仲間ですが、葉の形はまるで違います
三つ葉なのは下の方の葉だけで、上のほうは5枚葉
そして小さな葉が放射線状に出ています
1本の茎が伸びて、その先に10~20個たくさんの花が咲きます
車輪や笠のように見えるため「車軸草」「阿弥陀笠」「菩薩草」とも呼ばれます
本州北部から北海道まで、海岸の岩場や山地の乾燥した場所に自生しています
【ワスレグサ/カンゾウ】

7~8月にオレンジ色の花が咲き、草丈は80cmくらい
ユリ科の多年草
花は一日しか咲かないので、英語ではDaylily(デイリリー)と呼ばれています
特に日本は「ユリ大国」と呼ばれるほど、野生のユリが多い国です
そのため開花時期に探すと、河原などに自生しているのが見つかる場合があります
秋に咲くかわいい雑草

秋バラと同じころに咲くかわいい雑草は、バラを引き立ててくれます
そして花が少なくなる時期に、彩りを添えてくれる草たちでもあります
【ヨメナ】

7~10月に薄紫や白い花が咲き、草丈は50~100cm
キク科の多年草で、可憐な花を咲かせる野菊の一種です
本州の中部から九州までに生えています
やや湿った場所を好み、地下茎で増えるため群生することがあります
そのため駆除するのが難しい雑草ですが、優し気で風情のある花です
【ハギ】

7~10月に赤紫の花が咲き、草丈は100~150cm
マメ科の落葉低木で、茎が木質化して硬くなります
根元から多くの茎が伸びてきて、先端は垂れ下がります
たくさんの花が付くので、庭木の足元に植えておいても綺麗です
しかもマメ科なので、緑肥としても使えます
ハギは秋の七草のひとつです
中秋の名月に飾るのが「ハギの花」と「ススキ」
そして「月見団子」に添えて月を眺めるという風習がありました
【ゲンノショウコ】

7~10月に白い花が咲き、草丈30~50cm
フウロソウ科の多年草で、綺麗な花が目を引きます
赤紫または白に薄紫の線が入った花びらが特徴的です
日本中の山や道端など、日当たりの良い場所に生えています
【セイタカアワダチソウ】

10~11月に黄色い花が咲き、草丈は100~250cm
キク科の多年草で、北米原産の帰化植物です
そして切り花などの観賞用として日本に入ってきました
肥沃な土地だと350~450cmにも達することがあります
さらに地下茎で増えるので群生しやすく、要注意外来生物に指定されています
サポニンを含むので石鹸として使え、薬草風呂として浴槽に入れると泡立ちます
花粉症の原因となる「ブタクサ」に似ていますが花粉は飛びません
セイタカアワダチソウは風媒花ではなく虫媒花だからです
雑草を庭に活かす方法
雑草も庭に活かすと、手間がかかりません
背が高くならない草、地面を這うように伸びる草は、グランドカバーとして使えます

背の低い雑草は、抜かずに残すとグランドカバーとして活かせます。背が高くなる草だけ抜いていけばいいからです。地面を覆うように草が生えていれば、他の雑草は生えなくなっていきます。
雑草で土質を判断することもできます
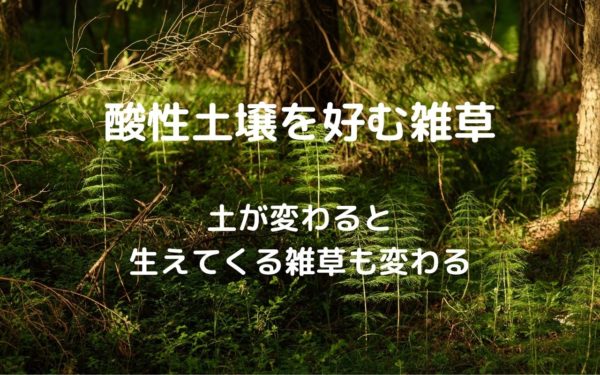
酸性土壌とは、ミネラル分の少ない土質のこと。日本は雨が多いためにミネラル分が流出し、酸性土壌になりがちと言われます。反対にミネラル分が多い土質が、アルカリ土壌です。ミネラルには、カルシウム、リン、カリウムなどがあります。例えば地中海地方に多い石灰岩はカルシウムなので、アルカリ土壌です。
当ブログの記事を整理してアマゾンKindleの電子書籍と紙の本で出版しています

Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください