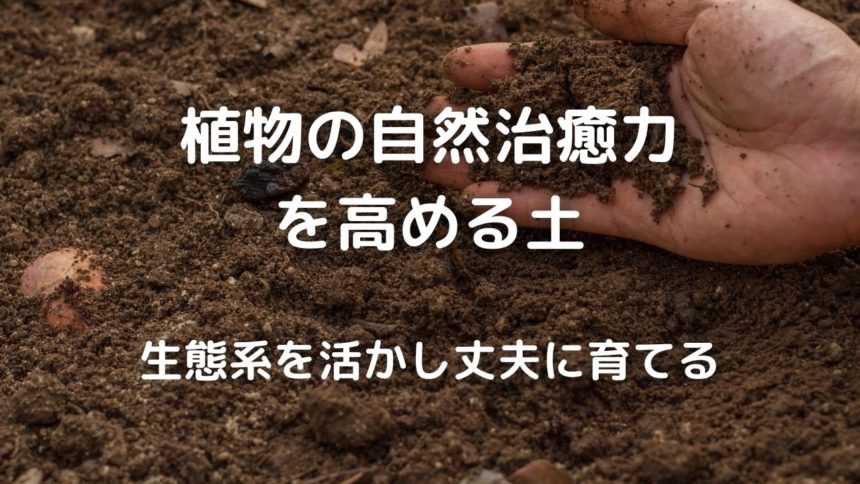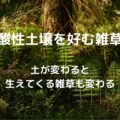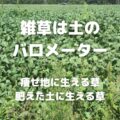家庭菜園の土作りに最適なのが、秋です
なぜなら冬の寒さで病害虫を死滅させ、春までに土壌改良ができます
例えば、土を掘り起こし、堆肥を入れておくことです
土壌改良には時間がかかるため、植え付け1か月前には済ませておきます
そして野菜の収穫後は、足りなくなった養分を補う必要もあります
最初に行う家庭菜園の土作り

これから家庭菜園を始める場合には、まず土を耕す必要があります
植物が植えられていない土は、固く締まっているからです
土の中には、ゴミや大きな石もあるため、それらを取り除きます
土の中に有益な微生物を増やし、病原菌を減らすことも大事です
- 土を耕す
- もみ殻燻炭と酢をまく
- 枯葉や落ち葉を敷く
- 米ぬかをまく
- 土を戻して枯草を敷く
- ネギの苗を植える
米ぬかは有益な微生物を増やし、ネギは病原菌を減らします
【土を耕す】
まずは地表の草を刈り取り、土を耕して大きな石などを取り除きます
深さ「30cm」ほど土を掘り出すと、土中に空気も入ります
地面にスコップを突き刺し、そのまま持ち手を押し下げて土を持ち上げます
掘り上げた土は横に置いておきます
庭や菜園の奥から始め、「後ろ向き」に耕していくと効率的です
【もみ殻燻炭と酢をまく】
土を掘り出した地面の底に「もみ殻燻炭」をまきます
分量は土が隠れる程度で十分です
その上から100倍に薄めた「食酢」を振りかけます
【枯葉や落ち葉を敷く】
土の底には「枯草」を敷いておきます
これは水はけを良くするためです
枯草は「ススキ」など「茎が空洞」になった「イネ科」の草が適しています
茎に空洞のない「稲」は腐りやすいため適していません
【米ぬかをまく】
土作りに使う「米ぬか」は、微生物のエサとなるものです
微生物の種類が増えると、病原菌ばかり増えることがなくなります
枯草の上から薄く「米ぬか」をまきます
その上から、また「籾殻燻炭」をまき、100倍に薄めた「酢」を振りかけます
【土を戻して枯草を敷く】
掘り起こした土を戻して穴を埋め、その上から「ススキ」などの枯草を敷いておきます
これは地表の乾燥を防ぐためです
ところどころに「竹」や「木の棒」などを置いて、枯草が風で飛ばされるのを防ぎます
【ネギの苗を植える】
土の準備ができたら、ネギの苗を植えておきます
なぜなら、ネギが病原菌を抑える役割を果たすからです
不耕起栽培では、土を掘り起こすのは最初の1回だけ
その後の4~5年は土を耕しません
それはミミズなどの土壌生物と土中の微生物を安定させるためです
植え付け前に行う家庭菜園の土作り

種まきや苗の植え付けをする前に必要なのが、ペーハー調整です
なぜなら土のペーハーが不適切だと、生育しにくい野菜もあるからです
例えばアルカリ土壌が原産地の西洋野菜やハーブには、石灰を加える必要があります
逆に酸性土壌を好むブルーベリーなどには、ピートモスを加えます
雨の多い日本は酸性土壌になりがちです
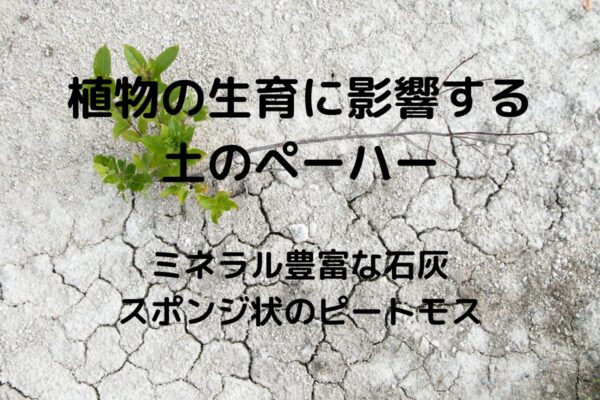
土壌のphが酸性かアルカリ性かで、植物の生育に大きな影響を与えます。なぜなら土に含まれるミネラルの分量が関係しているからです。そして必要なミネラルの分量は、植物によって異なります。ミネラルが多い土は「アルカリ」度が高く、少ないと「酸性」度が高くなります。
生えてくる雑草で、ある程度の判断をすることも可能です

火山の噴火などで裸地になっても、コケ類なら空気中の水分だけで生育できます。コケ類によって土に養分や水分が蓄えられると、他の植物も芽を出します。そうして次第に土が肥沃になるにつれて、生えてくる雑草が変わります。
とはいえ様々な野菜や草花を育てていると、ペーハーは変化します
そのため酸度計で測るのが確実です
収穫後に行う家庭菜園の土作り

野菜を収穫した後は、捨てる部分で堆肥をつくることができます
簡単に早く堆肥が作れるのが、木枠で作ったコンポスターです

堆肥作りのための容器は、手作りすると便利です。板を組み合わせて四角い枠を作るだけなので簡単。材料を入れながら積み重ね、かさが減ってきたら一段ずつ外して材料を移します。すると自然と上下が入れ替わり、面倒な切り返し作業の完了です。簡単なうえに、早く堆肥ができあがります。
そして野菜くずからは、土壌改良効果の高い植物性の堆肥が作れます

土壌改良の目的で堆肥を使う場合は、植物性の堆肥が適しています。なぜなら植物性堆肥は、窒素などの養分や微生物のバランスがいいからです。それに比べ動物性堆肥は、養分が多いだけに病原菌や害虫も集まってきます。
土作りで使う堆肥には、土壌改良と肥料効果の二つの目的があります

堆肥の効果は、大別すると「土壌改良」と「肥料効果」の2つです。そのため目的に応じて堆肥の種類は異なります。例えば、植物を植える前には土壌改良、植物が成長する時期には肥料として。そして土壌改良と肥料とでは、堆肥に使う材料も違います。
当ブログの記事を整理してアマゾンKindleの電子書籍と紙の本で出版しています
Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください