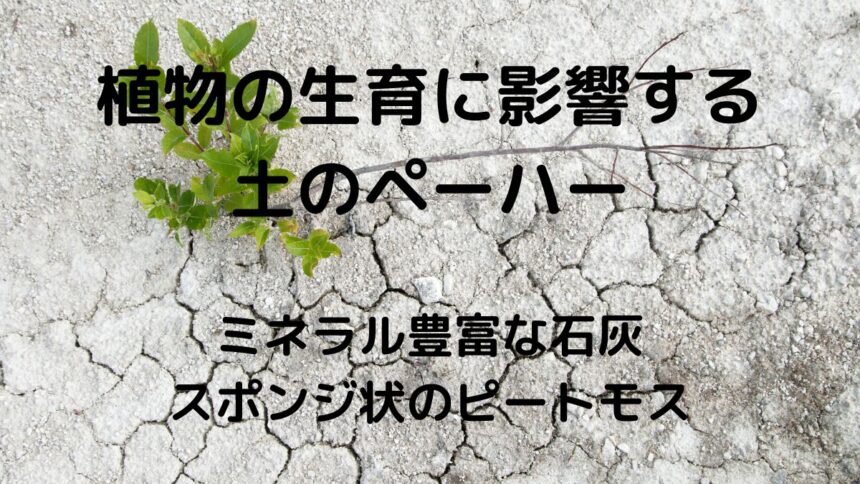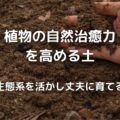土壌のphが酸性かアルカリ性かで、植物の生育に大きな影響を与えます
なぜなら土に含まれるミネラルの分量が関係しているからです
そして必要なミネラルの分量は、植物によって異なります
ミネラルが多い土は「アルカリ」度が高く、少ないと「酸性」度が高くなります
土壌のph調整をする方法

生育状態が悪い場合、土壌のphが原因という場合があります
そんな時には「石灰」や「ピートモス」を土に加えてペーハー調整します
- 石灰で「アルカリ度」を増す
- ピートモスや鹿沼土で「酸度」を増す
とはいえ石灰やピートモスを加え続けていると、バランスが傾きがちです
作物を植えて収穫した後には、土が元の状態に戻っていることもあります
そのため新たな植物を植える前に、pH測定器でペーハーを測ってみると失敗しません
【土をアルカリ性にする石灰】
アルカリ度を1pH上げる場合、以下の比率が目安です
土100リットル(直径50cm×深さ50cmくらいの量):石灰200~250g
石灰を混ぜてから土の酸性度が中和されるまでには「10~14日」くらいかかります
そのため「苗を植え付ける前」に準備しておく必要があります
- 「消石灰」なら植え付け「2週間以上前」
- 「苦土石灰」なら植え付け「4~5日前」
消石灰は、海苔の乾燥剤などに使われているものです
●消石灰と苦土石灰の違い
石灰には「苦土石灰」と「消石灰」があり、アルカリ分の度合いが異なります
消石灰とは「カルシウム」が主成分の石灰のことで「アルカリ分が65%以上」あります
カルシウムが骨の成分になるように、土を固くする成分です
そのため消石灰を多量に加えると、土が固まって根が伸びられなくなります
苦土石灰とは「マグネシウム(苦土)」を含む石灰のことで「アルカリ分は50%以上」です
マグネシウムが含まれるため、カルシウムとのバランスがとれています
【土を酸性にするピートモス】
酸性土壌を好むブルーベリー栽培などでは、土にピートモスを加えます
ピートモスは、砂地に混ぜて、水持ちを良くする場合にも使われます
なぜならスポンジ状になっているため、多くの水を含むことができるからです
天然のミズゴケが腐食したもので、温室効果を防ぐ効果もあります
天然資源のため、採取して枯渇しないよう、北海道やカナダなどで栽培されています
土壌のphとは?

ペーハーは、0~14の数値で表されます
例えば、中心の「7」が「中性」です
そして7より低いほど酸性、7より高いほどアルカリ性が高いことを示します
ペーハーを調べるために使われるのが、リトマス試験紙です
液体に浸すと「酸性(0~6.9)なら赤」「アルカリ性(7.1~14)なら青」に変色します
【土壌のphを左右する条件】
カルシウム、カリウム、リン、といったミネラルは、植物の大切な養分です
土のペーハーを左右するミネラルの量を左右するのが、土を構成している「岩石の性質」「腐植の量」です
例えばカルシウムでできている石灰岩が多いと、アルカリ土壌になります
そのため石灰岩の多い地中海沿岸では、アルカリ土壌を好むハーブが多く生えています
ギリシャの白い家は、豊富に採れる石灰を使った漆喰が壁塗りに使われるためです
海苔の乾燥剤などとして使われている白い粉末が、「消石灰」と呼ばれるカルシウムです
さらにペーハーは、「降雨量」「日照」「温度」などによっても変わります
例えば雨の多い日本はミネラル分が流されるため、酸性土壌になりがちです
そのため欧米の水はミネラル分が多い硬水で、日本の水はミネラル分の少ない軟水です
原産地の土質に応じて、植物が生育しやすいペーハーは異なります
そのため植物に応じて土のペーハー調整をすると、よく生育します
【アルカリ土壌を好む植物】
アネモネ、カスミソウ、キンギョソウ、キンセンカ、クリスマスローズ、ゼラニウム、シクラメン、スイセン、スズラン、デルフィニウム、ワスレナグサ、ライラック、ホウレンソウ
これらはpH7以上のアルカリ土を好む植物です
そのため土に「石灰」を混ぜてペーハー調整をすると、生育が良くなります
【酸性土壌を好む植物】
ツツジ、サツキ、青花アジサイ、ブルーベリー
これらはpH5.0くらいの酸性土を好みます
例えばトマトの場合なら、pH5.5~7.5くらいの弱アルカリ性です
土に「ピートモス」など加えてペーハー調整をすると、よく育ちます
とはいえ土のペーハーは、肥料を加えたり、植物を植えたりすることでも変わります
そのため新たに植物を植える場合は、ペーハーを測り直すと確実です
土壌のphを調べる方法

土壌のphを測定する時に使うのが「pHメーター」です
地面に差すだけなので簡単に測定できます
あるいは土壌のphを知る手がかりとなる植物もあります
【アルカリ土壌でしか育たない二十日大根】
土が酸性かアルカリ性かを調べる簡単な方法が「二十日大根」の種を蒔いてみること
なぜなら二十日大根は、アルカリ性の土でなければ生育しないからです
20日で収穫できるほど成長が早いので、すぐに結果が分かります
まず生育の差を見るために、二種類の培養土を用意します
- 「庭の土(50g)」と「脱脂綿」を、それぞれ小皿に入れる
- 水が溜まらない程度に、霧吹きで湿らせてから、種を30粒ずつ蒔く
- 土や脱脂綿が乾いたら霧吹きで湿らせる
すると数日で発芽するはずです
そして、よく発芽して成長すればアルカリ性、生育せず芽が枯れたら酸性と考えられます
あまり生育が良くないのは、塩分など他の要因の場合もあるので、あくまでも目安です
【酸性土壌に生える雑草】
自然と生えている雑草もペーハーを知る手掛かりになります
酸性土壌に生えてくる雑草があるからです
例えば「スギナ」や「ギシギシ」「アザミ」「スイバ」などが生えていたら酸性土壌の可能性があります
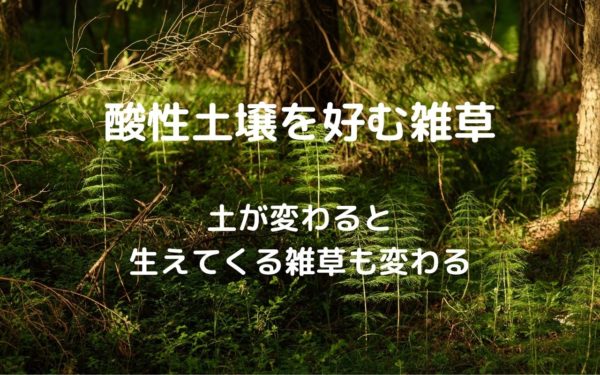
庭に生えている雑草は、土の性質を判断する指標にできます。なぜなら自然界では「土質に合った」雑草しか生えられないからです。土の中には無数の種が落ちていて、環境に合ったものだけが芽を出します。
とはいえ二十日大根も雑草も、ある程度の指標を示すだけです
そして、適正な土壌のph値は、植物によって微妙に異なります
当ブログの記事を整理してアマゾンKindleの電子書籍と紙の書籍で出版しています
Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください