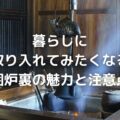キッチン収納は、整理・整頓・整列、の順番に片づけるのがポイントです
なぜなら、最初にグルーピングすると、置き場所を決めやすくなるからです
例えば、まずは調理や洗い物など、作業別に使う物を「整理」します
次に、それぞれ使いやすい置き場所に「整頓」し
最後に見やすいよう「整列」させて収納という順番です
キッチン収納は整理から

まずは、キッチンになくてもいいものを追い出すとスッキリします
なぜならキッチンに置くより、別の場所に置いた方がよい調理器具や食器もあるからです
見直す場所は2か所あります
- 吊戸棚に入れてある普段は使わないもの
- 電源の近くにあるキッチン家電
普段は使わない物まで狭いキッチンに置くのはスペースの無駄です
電源の近くにある家電も、別の場所でいいかもしれません
【キッチンに置かなくていいもの】
食事の時に使う物は、テーブル近くのほうが便利です
- お茶やコーヒー用品
- 卓上コンロ
- チーズフォンデュセット
そして食事中に使う食器類もキッチンに収納する必要がありません
- 取り皿、ごはん茶碗
- スプーンやフォーク、箸
例えば、テーブル下や近くに「棚」や「ワゴン」を置いて、そこに収納
後片付けの時にトレイで食卓から運び、洗い終わった食器は元の場所へ
食事の時しか使わない物を食卓へ移動すると、空いたスペースに調理道具や調味料などを収納できます
しかもキッチン家電を調理場付近に置くと、すぐ汚れます
丸洗いできるものでもないので、キッチンには置かないほうが手入れが楽です
- 炊飯器
- ホットプレート
- タコ焼き機
- 電気ケトル
例えば炊飯器なら、キッチンで使うのは、米を入れて洗う中の釜だけ

むしろ食卓の近くに置いたほうが、ごはんをよそいやすいし
おかわりする時にもキッチンまで行かずに済みます
例えばキャスター付きワゴンに載せて、食卓の下に入れておくと邪魔になりません
するとワゴンに「御飯茶碗」「へら」「箸」なども一緒に収納しておけます
「コーヒーメーカー」「電気ケトル」も、キッチンで必要なのは水を入れる時だけ

むしろ、お茶やコーヒーを飲む場所にあるほうが便利です
ペットボトルの水やウォーターサーバーがあれば、その場でOK
リビングの食器棚やワゴンにカップなどと一緒に置いて、お茶やコーヒー専用コーナーにできます
【キッチンに置くもの】
調理中に使うのは、下ごしらえをする家電だけです
- 食材を切ったり混ぜたりする「フードプロセッサ」
- 解凍や過熱をする「電子レンジ」
これらはキッチンにあるほうが便利です
そしてキッチンで必要な食器は、料理を盛り付ける皿やボウルだけ
キッチンに収納場所がない場合には、ワゴンをプラス

しかも、こまごましたものの収納にも適しています
保存用の食品やストック品の置き場所にもできます
重たい液体類や米などはキャスター付きワゴンに
キッチンの隅などに置いても移動しやすく、詰め替えする時などに便利です
そのためワゴンの上には物を置かずに開けておくと詰め替え作業しやすくなります
キッチン収納を整頓する

整頓のポイントは、それぞれ物の置き場所を決めること
そのためには、使いやすい場所に置くことが大事です
ところが頻繁に使っていると、体で覚えてしまい、使いにくさに気づかなくなります
棚板の位置と高さは、使う頻度によって決め、しょっちゅう使う物は取りやすい高さに
- 立ったまま腕を下した時の手の位置
- 腕を上げた時の手の位置
この間が最も使いやすい場所です
例えば身長155cmの私なら「床から60~180cm」の高さ
そこに最も頻繁に使うものを置きます
重たい物を上のほうに置くと棚が不安定になるし、落ちた時に危険です
- 重い鍋、米などは下の棚
- 軽いフライパン、乾物などは上の棚
【吊戸棚の使い方】
キッチンの吊戸棚は、軽くてさかばるストック品の収納場所に
- キッチンペーパー
- ラップ類
- ティッシュ
箱などに入れて下の方に取っ手を付けておけば、引き出して取ることができます
例えば吊戸棚の収納にピッタリなボックスがこちら
下の方に取っ手が付いているので、楽に取り出せます
シンプルな白だから、オープン棚でも綺麗に収納できます
そして普段に使う大きな食器類を吊戸棚に入れるなら「手が届く高さ」まで
高い位置に入れるのは「年に一度」くらいしか使わないような食器だけ
例えば、お正月やクリスマスにしか使わないようなものです
●ストック食品の収納
ストック食品は頻繁に出し入れしないので、手が届きにくい場所でも構いません
- 「干しシイタケ」「昆布」「ゴマ」「海苔」など乾物や軽い調味料なら吊戸棚に
- 「液体の調味料」や「粉類」など重いものは下に
それぞれカゴや箱にまとめて入れておけば、補充する時だけ出せば済みます
●調味料の収納
調味料は「小分け」して、「使う場所に」分散して収納
あちこちに置いたほうが使いやすく、余分なストックを買い置きする必要もなくなります
頻繁に使う「塩」「醤油」「酢」「油」なども小分け収納が便利です
- 下ごしらえ用は「シンク」近くに
- 調理の仕上げ用は「ガス台」近くに
- 食事中に使う分は「食卓」に
しかも1本を全て小さな容器に小分けして入れ替えれば、本体の容器は捨てられます
そして食卓で使う分はテーブルの上や近くの棚に

醤油や酢なら冷蔵庫に入れておき、調理する時に食材と一緒に出して
あちこちにあれば、買い置きを忘れていても別の場所から持ってくれば済みます
【細々したものの収納場所】
細々した小さなものが多いお弁当グッズは専用の引き出しやカゴを決めて収納

一か所に集めると手際よく準備できます
- お弁当箱
- 間仕切りグッズやピック類
- お弁当を包む袋や布
例えばカゴなら電子レンジの上、キッチンワゴン、冷蔵庫の上などに置けます
軽いものなら「紙袋」や「カゴ」に入れて、S字フックで吊り下げ収納でもOK

上のほうなら空いてるスペースがあるものです
そのため予備のスポンジやブラシなどの収納にも便利です
小さなビニール袋はティッシュボックスに収納
一枚ずつ取り出しやすく、ギュッと押し込んでおくだけだから入れるのも簡単です
例えばプラスチック製のティッシュボックスならシンク近くに置けます
【ストック食品や調味料の収納場所】

ストック食品は同じ容器に入れて収納すると重ねたり並べたりできます
そして保存容器は一袋が全部入る大きさのものを用意
なぜなら入りきらないと別に収納しなければならなくなるからです
- 「粉類」は口が広い容器に:小麦粉、パン粉、砂糖、塩
- 「液体」は口が細い瓶に:醤油、油、酢、酒、みりん
- 「乾物」は密閉容器に:パスタ、干し椎茸、ドライフルーツ
容量が少ないものも同じ容器に入れたほうが重ねられます
中途半端に空いたスペースには隙間収納が便利です
10cmくらいの隙間なら、ラップ類が入ります
オープン棚なら目障りにならないように
例えばシンプルな容器にカトラリーを入れて収納

グルーピングして置き場所を決めるのがポイントです
あるいは缶詰や消耗品のストックなどをまとめて置く場所としても使えます
キッチン収納を整列させる

キッチン収納の棚の奥行は20~30cmくらいが物を置きやすく、取りだしやすいサイズです
前後に物を置かず「横1列に並べる」のが基本
なぜなら前後に入れると奥のものが取り出しにくいからです
さらに片付けるのも億劫になります
【食器棚の収納法】
並べるのは大きめの皿やボウル、重ねるのは「同じ種類」だけにします
違う種類の食器を重ねると、下の食器が取り出しにくくなります

例えば棚板を増やして「1段に1種類」ずつ並べた方が出し入れが楽です
棚の手前側にスペースが空いていると、つい他のものを置いてしまいがち
細々したものが置きっぱなしになると、整理整頓できなくなってしまいます
棚の奥行より小さなものはカゴに入れて、奥行に合わせたカゴの中を仕切ります
小鉢や小皿なら重ねて「引き出し」に収納するほうが、見やすく取りやすくなります
その時には間にクシャっとさせた「ラップ」をはさむと食器同士がぶつかりません
棚に収まらない大きな皿は「立てて収納」すると省スペースです
ファイルボックスなどに入れ、間に1枚ずつ「厚紙」を挟んでおけば傷つきません
カップとソーサーは別々に、それぞれ重ねておくと取りやすくなります

あるいは、カップとソーサーをセットで収納するなら、カップの上にソーサーを乗せて重ねます

皿とカップの「上下を逆」にすると、オープン棚でもカップにホコリが入りません
使う時には1客ずつセットで取り出せるので便利です
【保存食品の収納法】
棚に並べると見やすく、残量も一目で分かります

あるいはファイルボックスに「立てる」収納も省スペースです

- レトルト食品
- 海苔
色や形がバラバラなものはカゴに入れて

棚+カゴの定番パターン
洗えるカゴを使うと手入れが楽です
透明でないカゴにはラベルに内容物を書いておくとパッと見つけられます
【冷蔵庫を使いやすくする収納】
冷蔵庫の中は、油断すると調味料や食材でベタベタしがち
そのため細々したものは、まとめてサッと取り出せると、調理も掃除も楽です
倒れやすいチューブ類は、立てておけるとストレスなく出し入れできます
●倒れやすい調味料類の収納
収納しにくい「マヨネーズ」や「ケチャップ」は口が細いドレッシングボトルが便利

倒れないので冷蔵庫内が汚れません
蓋を外して詰め替えでき、本体部分を手で握れば少しずつ出せます
ゴマなど入れておくと、少しだけ振りかける時に便利です
ボトル本体が透明なら中身が分かりやすくて使いやすい
100円ショップに売ってます
●野菜室の収納
葉物野菜などは、立てて収納したほうが長持ちします

紙製の袋に入れておくと仕切りになります
買ってきた時のビニール袋そのままでもOK
上のほうを開けておけば取り出しやすいし、残量も分かります
●食品の保存容器
冷蔵庫の中は「ガラス」や「金属製」ケースが最適

食品が冷えやすいので長持ちします
ステンレスの蓋つきケースなら重ねられます
トレイに並べておけば出し入れも簡単
プラスチックと違い、色や臭いが移らず、油汚れもスッキリ落ちて気持ち良く使えます
別売りのザルもセットにすると水切りできます
100円ショップにも様々な食品ケースが売られています
プラスチック製よりも、蓋つきのガラスケースがおすすめです
大きなものは200円の場合もありますが、スッキリ洗え、そのまま食卓にも出せます
冷凍食品などは、プラスチックケースに立てられます
下調理した食材も、ジップロックなどで平たく冷凍しておけば、立てて収納できます
【キッチン収納アイテムの選び方】
キッチンの収納アイテムは、何を入れるか決めてから購入すべきです
買ってから入れる物を考えると、中途半端になって結局なんでも入れてしまいます
例えば、おしゃれなスパイスラックとかワインラック
キッチンに置いてみたら、ラックそのものが邪魔だったりします
まずは使いやすい置き場所と、頻繁に使うものの量を確認
それがピッタリ収まる収納アイテムを探すのが失敗しないコツです
キッチンに置くものは、動線に沿って配置すると作業しやすくなります

作業の「動線」に合わせて物を配置すると、調理はとっても楽になります。動線に沿って動けば、無駄なく、効率的に作業できるからです。キッチンの動線は、調理の手順に合わせることがポイント。食材を出す、調理する、盛り付ける、順番に配置してあるとスムーズです。
キッチンは、その家の清潔度が現れる場所
掃除が面倒にならない工夫で、常にキレイにしておけます

キッチンは、最も衛生管理をしておきたいのに、最も汚れやすい場所。使用頻度が高く、水と油とホコリで汚れ、物が多くて掃除しにくいからです。まずは分別ごみの置き場所を確保することで、余計な物が溜まるのを防げます。買い物した時のパッケージ、使い終わった容器や生ごみは、すぐ捨てることが肝心。