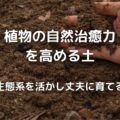堆肥の作り方には「密閉式」と「開放式」の2つがあります
密閉式は、臭いの発生を抑えられるので、キッチンなど室内での堆肥作り向きです
開放式は、早く大量に堆肥が作れるので、庭など屋外で堆肥を作る場合に向いています
例えば畑など広いスペースなら「地面に穴を掘って埋める」だけ、という堆肥の作り方も可能です
さらに落ち葉だけなら、穴を掘らずに地面に山積みしておいても自然と堆肥になります
ただし「虫」や「臭い」が発生することがあるので、住宅密集地の庭には不向きです
堆肥の作り方で最も大切な「発酵」

屋外では、容器に材料を入れたら定期的に混ぜて、空気を入れる堆肥の作り方が一般的です
なぜなら空気を入れると好気性菌が活性化して、分解が早く進むからです
さらに発酵促進剤として「米ぬか」などを振りかけると、早く堆肥にできます
- 堆肥の材料を容器に入れて、米ぬかなどの補助材料を振りかける
- 材料と発酵促進剤を交互に積み重ねる
- 定期的に上下を入れ替えるようにして混ぜ、水分の調整をする
発酵が始まると「60℃」くらいの高温になってくるはずです
そうしたら上下をひっくり返すようにして混ぜ、切り返しを行います
この時に、もし乾いているようなら水を足し、水分が多ければ乾いた材料を足します
そして1週間ごとに混ぜ返していると「40℃」くらいに安定してきます
さらに、そのまま「3か月」ほど熟成させると完熟堆肥の完成です
通常は「1~2カ月おき」に混ぜておくと、「半年から1年」で堆肥が完成します
分解している間はカビの臭いがしますが、完成すると土の匂いになります
【堆肥が完成している目安】
堆肥が完成しているかどうかの目安は3点あります
- 色は中まで黒く、均一になっている
- かすかにカビの臭いがあっても腐敗臭はない
- 握ってみると、しっとりして固まり、ほろほろ崩れるくらいの硬さ
空き瓶などに堆肥と水を入れると、完熟しているかどうかを調べられます
水を入れた容器に堆肥を少し入れた時に「沈む」ようなら熟成しています
堆肥より多めの「水」を加えて「蓋」をし、「10日」くらい放置しても臭いがなければ完熟しています
ところが腐った匂いがしたり、カサカサしている場合は、まだ完成していません
切り替えしと水分調整をしながら、さらに時間をかける必要があります
- 乾燥してカサカサしているようなら「水」をかけて水分を補う
- 水分が多くベタベタしているなら「土」「枯葉」「もみ殻」など「乾いた材料」を加える
水分量は、手で強く握った時に水が滴り落ちないくらいが適量です
【トラブルが出ない堆肥の作り方】

堆肥を作っている時に発生しやすいのが「虫」「カビ」「臭い」です
これらは、順調に発酵している時には発生しません
ですから発生した時には、何らかの対処が必要です
●虫を抑える堆肥の作り方
予防策は「虫除けネット」を掛けておくことです
生ごみなどを投入した後は、すぐに混ぜて覆いをしておきます
投入前の生ごみは、できるだけ「水けを切る」ことも大事です
虫が付いた時には「石灰」や「土」を振りかけます
堆肥が発酵して「熱」を発するようになれば、虫は死滅します
●カビを抑える堆肥の作り方
白いカビは発酵が順調なしるしなので気にする必要ありません
黒カビや青カビが発生した場合には「石灰」や「土」を掛けて混ぜておきます
悪臭がある場合には、カビの部分を取り除いて土に埋めるか、ゴミとして処分します
●臭いの出ない堆肥の作り方
「茶殻」「コーヒーかす」「もみ殻燻炭」「重曹」を加えると臭いを抑えられます
腐敗しやすい「肉類を入れない」ことが予防策です
堆肥の作り方における「有機物」の役割

堆肥の材料となる有機物とは、微生物のエサとなる動植物のことです
それに対して金属や鉱物などの無機物は、微生物に分解されません
有機物は「動物性」「植物性」の2種類に分けられます
- 植物性:野菜、枯れ葉、細かな木片、籾殻、米ぬか、雑草、稲わら
- 動物性:牛糞、鶏糞など動物の糞
どちらも「土壌改良」の効果がありますが、動物性の有機物のほうが「肥料」効果が高まります
【動物性の堆肥】
動物性の堆肥とは、主に動物の糞を使ったものです
草食動物の糞は、植物性堆肥よりは肥料効果がありますが、土壌改良に適しています
雑食の豚や鶏の糞は、窒素などの養分が多いため肥料効果が高まります
- 牛糞堆肥(土の団粒化を進め、良質な土に変える)
- 馬糞堆肥(繊維質が豊富で、土の通気性、排水と保水を良くする)
- 豚糞堆肥(肥料分が多く、繊維質は少なめ)
- 鶏糞堆肥(肥料分が多く、即効性のある肥料として使う)
牛糞や鶏糞などは、一般家庭では手に入らないので市販のものを買うしかありません
さらに牛糞や鶏糞は、養分が多いだけに、使い方によっては逆効果になることがあります
【植物性の堆肥】
家庭では、植物性の有機物を使った堆肥の作り方が適しています
なぜなら材料が手に入りやすく、養分が過剰になる危険性が低いからです
例えば、野菜クズや刈り取った草などが使えます
植物性の堆肥は肥料効果が少ないですが、「種まき」や「苗の植え付け」時に適しています
- 植物の成長を促す
- 連作障害のリスクを減らせる
- 養分や微生物のバランスが崩れにくい
- 病害虫のリスクが少ない
- 発芽する時の障害も少ない
堆肥作りに使える植物性の有機物は「落ち葉」「樹皮」「雑草」「もみ殻」「野菜くず」など
庭木を剪定した時の小枝や、植物の根なども使えます

土壌改良の目的で堆肥を使う場合は、植物性の堆肥が適しています。なぜなら植物性堆肥は、窒素などの養分や微生物のバランスがいいからです。それに比べ動物性堆肥は、養分が多いだけに病原菌や害虫も集まってきます。
堆肥の作り方における「微生物」の働き

堆肥の作り方で大事なのは、腐敗ではなく発酵させるということです
腐敗と発酵の違いは人にとって有害がどうかで、腐敗しても、いずれ発酵して土に還ります
例えば、山や森では、落ち葉や虫の死骸などが堆積して、自然と分解されています
とはいえ家庭で堆肥を作る場合には、腐敗臭は抑える必要があります
そのため水分や空気の量を調節し、微生物の活動を活性化させます
堆肥を作る微生物には、酸素を好む「好気性」と、酸素を嫌う「嫌気性」の2種類がいます
- 好気性菌(酸素がある場所でのみ活動する)
- 嫌気性菌(酸素がない場所でのみ活動する)
堆肥の作り方で重要なのが、これらの菌を使い分けることです
【好気性菌の働き】
好気性の微生物には「放線菌」や「糸状菌」などがあり、発酵中に発生する白いカビが糸状菌です
材料を混ぜて空気を入れることで好気性菌を増やし、分解を早めます
ところが好気性菌は、急速に分解を進めるためにガスを発生させます
このガスが腐敗臭となり、窒素分を空中に放出してしまい、有害物質が作られることもあります
そういった腐敗を抑えるのが嫌気性の菌です
【嫌気性菌の働き】
嫌気性の微生物には「乳酸菌」「酵母菌」「メタン菌」などがあります
これらの菌が放出するエチレンによって、好気性菌や病原体の活動が抑えられます
ですから、腐敗臭を抑え、有害物質を無害化するために必要なのが、微生物のバランスです
空気のあるところでは「好気性菌」が活性化して分解が進みます
そして発酵が始まると温度が上がり、病原菌や虫などは死滅します
発酵が終わり、有機物が完全に分解されると、堆肥の完成です
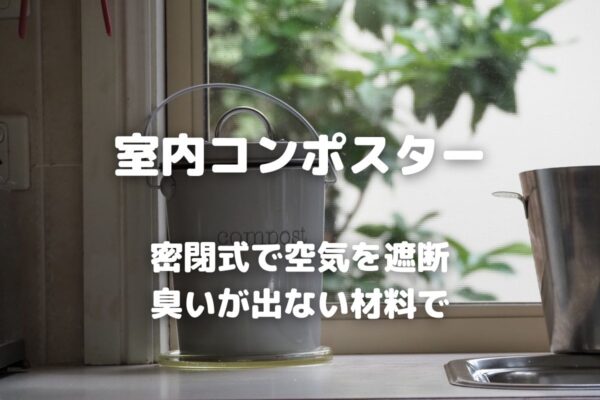
生ごみ堆肥を室内で作る場合には、密閉できる容器を使います。空気を遮断することによって、腐敗臭を抑えるためです。腐敗せずに「発酵」すれば、嫌な臭いはあまり発生しません。そのためには空気を嫌う「嫌気性」の微生物を増やすことがポイントです。
堆肥の作り方に適した「コンポスター」

コンポスト(compost)は「堆肥」
コンポスター(composter)は「堆肥を作る容器」のことです
材料を入れておくコンポスターは、市販のものが色々と売られています
【室内向きのコンポスター】
キッチンなど室内では、密閉式コンポスターを使った堆肥の作り方が一般的です
材料を入れたら蓋をして、溜まった水分は取り出します
そして容器いっぱいになったら、そのまま置いて発酵させて土に混ぜます
この場合は、土の中でも発酵が進むので、植物の根が触れない場所に埋めます
使う材料は、臭いが出にくい野菜クズが最適です
塩分は植物にとって有害なので、調理済みの食品は使いません
腐敗しやすく臭いを発生する肉や魚も入れません
底の方に水抜き栓が付いていて、溜まった液体を取り出して肥料として使えます
電動のコンポスターは高価ですが、臭いが出ず、早く堆肥化できます
自治体の補助金などが使える場合には、便利です
【屋外向きのコンポスター】
屋外で堆肥を作る場合には、開閉式のコンポスターが適しています
安価で手軽に使えるのが、地面に置くだけのコンポスターです
開放式のコンポスターでは、材料を混ぜて上下を入れ替える作業をします
そんな作業がしやすいのは回転式コンポスターです
材料を混ぜる時に、水や材料を加えて水分量を調節することもあります
そんな作業を楽にできるのが、木枠を積み重ねるコンポスターです

堆肥作りを手早く、簡単にできるのが、木枠を使ったコンポスター。廃材でも作れ、材料の上下を入れ替える「切り返し」作業も楽にできます。邪魔にならない場所に集めておくだけで、土壌改良に使える堆肥になります。
当ブログの記事を整理してアマゾンKindleの電子書籍と紙の書籍で出版しています
Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください