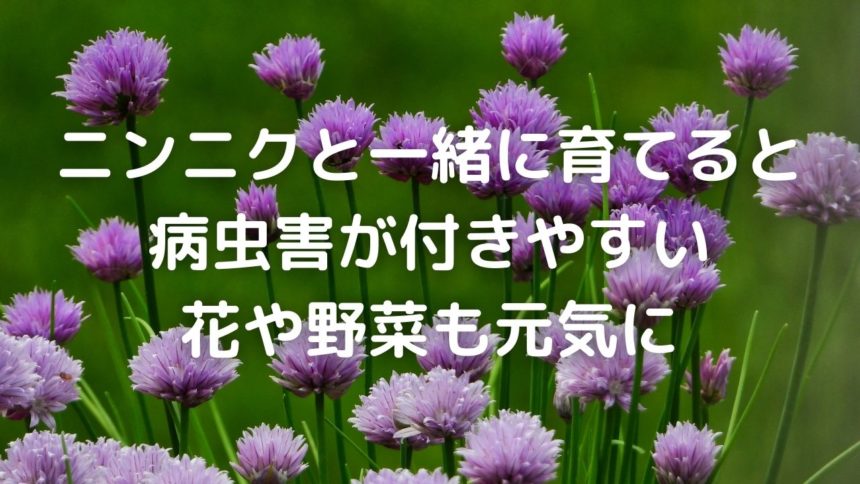ニンニク栽培では「肥沃な土」に植えることが大事です
なぜなら養分が足りないと、根が大きく育たないからです
例えばコンパニオンプランツとして植えたニンニクは、収穫できません
一緒に植えた野菜や草花に養分を取られてしまうためです
そのためニンニクを収穫するには、他の植物とは別に栽培する必要があります
そして「マメ科」や「キャベツ」とは相性が悪いので、一緒に植えないことも大切です
ニンニク栽培の方法

ニンニクは、暑さに弱く、霜には強く、同じ場所で続けて栽培できます
栽培の適温は「10~22℃」で、25℃以上になると休眠します
食用に市販されているものの多くは発芽抑制処理がされているので発芽しません
そのため植えつける時には「栽培用」を購入したほうが確実です
例えば「ホワイト六片」は、寒冷地系の代表種で、香りと風味が強いという特徴があります
冬眠して越冬してから発芽します
【ニンニク栽培の土】
ニンニク栽培には6.0~6.5くらいの弱酸性で、やや乾燥気味の土質が適しています
さらに水はけの良い土でなければ育ちません
そして保水性の高い粘土質の土を好みますが、過湿は嫌います
比較的、土を選びませんが、肥沃な方がよく育ちます
例えば夏野菜がよく育った跡地なら、そのまま植え付けしてOKです
とはいえ養分が少ない痩せ地の場合は、植え付け「1カ月前」までに土の準備をします
●1m四方の土に対して
・完熟堆肥(3~4リットル)
・籾殻燻炭(2~3リットル)
加える場合は必ず「完熟堆肥」を使います
なぜなら土中に「未熟な有機物」や「窒素」が多すぎると球が溶ける原因になるからです
土の酸性度が高い場合には、「苦土石灰」または「貝化石」を50~100gまきます
貝化石とは、貝類の死骸が堆積して化石になり、岩になったものです
牡蠣ガラのように、塩分を含まないというメリットがあります
養分の少ない火山灰土の場合には、バットグアノ100gを追加してリン酸分を補うと改善できます
まず全体にまいてから表面5cmくらいを耕して土となじませます
【ニンニクの植え付け時期】
ニンニクは、植えるのが早すぎると発芽せず、遅れると越冬できません
●ニンニクの植え付け目安
・最高気温が25℃以下
・地温20℃前後
越冬させるには、寒冷地なら葉が2~3枚、温暖地なら4~6枚のもの
そして大きい種球を植えます
種球が大きいほど初期の生長が良く、収穫サイズも大きくなります
【ニンニクの植え付け方法】
種球は1片ずつに分けてから植えます
植え付ける時には「同じ大きさの球」を揃えるのがコツです
なぜなら大小を混ぜて植えると、小さいほうが負けてしまうからです
さらに「薄皮をむく」と早く発根して大きく育ちます
まず植える場所の草を刈り取り「種球の2倍の深さ」の穴を掘ります
種球は「尖ったほうを上」に向けて、掘った穴の底に
そして土を埋め戻し、しっかり押さえておきます
さらに密に植えると根が協力し合って互いによく育ちます
例えば小さい種球なら3cm間隔で植えると、数は少なくても質の良いニンニクが採れます
- ジャンボニンニク:15~20cm間隔
- 大きい種球:12cm間隔
- 小さい種球:10cm間隔
- 極小の種球:3cm間隔
【植え付け後の管理】
植え付けしたら、両脇に「米ぬか」を薄くまきます
米ぬかを地面にまくのは9月中旬以降に
なぜなら、春から夏に米ぬかを地面に撒くと腐敗しがちだからです
油膜を張って土中の生物の呼吸を妨げることにもなります
そのため必ず草マルチの上からまきます
あるいは気温が下がっていく9月中旬以降なら、土に直接まいたほうが分解されやすくなります
そして米ぬかをまいた上から刈り取った草を敷いておきます
すると冬越ししたニンニクが生育し始める2~3月に球の肥大を促します
植え付けて1週間で発根し、2週間で発芽します
【越冬後の早春に行う手入れ】
2~3月、草が茂りすぎるとニンニクの生育を妨げます
そのため草は刈り取って、ニンニクの周囲に敷いておきます
他のユリ科野菜と比べてニンニクは、あまり養分を吸収できません
そのため球の肥大期には、こまめに追肥します
追肥は、敷いた草の上から「米ぬか」をまいて養分を補充すればOK
追肥のタイミングは「2枚目の葉」が伸び始めてから「5枚目の葉」が伸び切るまで
月1回のペースで追肥します
積雪地帯なら、降雪までに2回、雪解け後に2回の追肥
肥沃な土なら米ぬかの補充は不要です
- 養分が適切な場合 葉にツヤがあり、周囲の草と同じ色
- 養分が不足している場合 葉にツヤがなく、黄色っぽくなる
- 養分が多すぎる場合 葉の色が黒ずみ、錆び病などが出やすくなる
養分が多すぎる場合の対処法はないので、養分過多にならないよう注意します
ニンニクの「芽」を収穫する方法

ニンニク栽培では、脇から出てくる小さな芽は早めに取り除きます
そのままにすると球が大きくならないからです
小さい球が付いている方を抜き取り、葉ニンニクとして収穫します
葉ニンニクは炒め物などにすると美味しく食べられます
傷みが早いので店頭に出ることはありません
葉ニンニクを抜く時は、残す方が抜けないよう注意
残す方は手で押さえて、小さい方だけを抜き取ります
春先にトウ立ちした「蕾」も球の肥大を妨げるので、早めに収穫します
蕾になる前に茎を曲げてみて、柔らかい部分から切り取ります
切り取った茎葉はニンニクの芽として食べられます
球の肥大には水分が必要です
4~5月は肥大期なので、1週間以上雨が降らない場合は、たっぷり水やりします
水やりは「温かい日中」に、土の深くまでしみこむよう、数回に分けるのがコツです
ニンニクの「球」を収穫する方法

ニンニクの「葉先30~50%が枯れたら」収穫時期です
茎を持って抜き取ります
長く保存するには収穫のタイミングが大事
「晴天が3日」続いき、土が乾いた時に収穫します
水分が抜けて長く保存できるからです
【収穫後の処理】
ニンニクを抜き取ったら、根と葉を切り落とします
根は付け根から「茎は15cm」残して
茎を短く切ると発芽してしまいます
切り取った根や葉は地面に敷いておくと虫よけになります。
鱗片と茎との隙間が「2~3mm」の頃が収穫適期
球の底面が平らな状態です
鱗片と茎との隙間が開きすぎて球の底面が凹型になると遅すぎ
採り遅れると、茎が枯れて、抜き取る時にちぎれ、球が開いてしまいます
球が開くと発芽しやすく、保存がききません
鱗片と茎との隙間がなく、球の底面が丸く飛び出た形だと収穫には早すぎ
早く収穫すると腐りやすくなります
【ニンニクの保存法】
茎が付いたまま、数個ずつ麻紐などで縛るかネットに入れ、軒下に吊るして保存できます
収穫してすぐ「皮を1枚むいてから天日干し」します
乾燥してしまうと皮がむきにくくなります
皮をむかず、そのまま冷凍してもOKです
使う前に「水に浸して解凍」すると簡単に皮がむけます
鱗片に分けて皮をむき「オイル漬け」「しょうゆ漬け」でも保存できます
みじんぎりニンニク、赤唐辛子、塩をオリーブオイルに漬けたソースも便利
パスタに絡めるだけで「ペペロンチーノ」の出来上がりです
ニンニクは多くの野菜と混植でき、強い香り成分と土中での殺菌効果で病害虫を防ぎます
特に「イチゴ」「トマト」「ナス」「キュウリ」とは相性が良い組み合わせです

トマトとバジルは一緒に料理しても栽培しても良い組み合わせ。近くに植えると、互いに味を良くして風味を高めます。「ニラ」や「バジル」をトマトと一緒に植えると病害虫を抑えられます。
とはいえコンパニオンプランツとして他の野菜と混植する場合には50cm間隔で1本ずつ
近すぎると相手の植物が負けてしまいます
自然栽培おすすめ本
いつも参考にしているのが竹内さんの本
分かりやすいイラストと詳しい解説が満載です
当ブログの記事を整理してアマゾンKindleの電子書籍と紙の書籍で出版しています
Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください