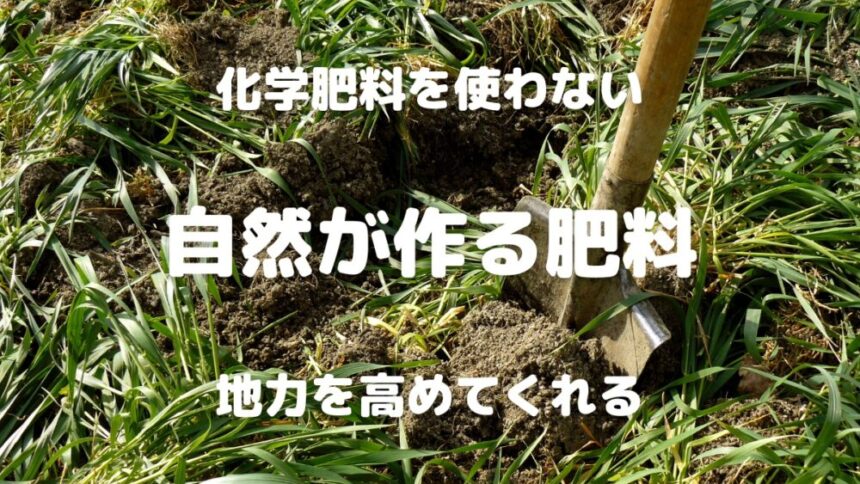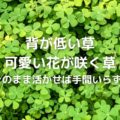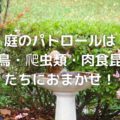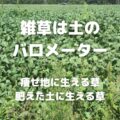自然栽培の肥料には「緑肥」と「堆肥」の2種類があります
緑肥とは、地中に窒素分を残すマメ科の植物などを植える方法
堆肥は、植物などを発酵させてから土に混ぜます
どちらも効き目は緩やかですが、植物を傷めず、安心して使える肥料です
植物の養分になると同時に、土を肥沃にして、地力を高めます
自然栽培の肥料~緑肥

自然栽培の肥料として簡単に使えるのが「緑肥」です
コンパニオンプランツのように一緒に植えたり、植え付け前後に植えたりします
野菜は1年で収穫して、翌年にまた種や苗から育てます
そのため土に養分を補充する必要も出てきます
野菜は収穫する時期が成長過程ごとに異なるので、必要な養分も違います
- 実を収穫する野菜(リン酸)
- 葉を収穫する野菜(窒素)
- 根を収穫する野菜(カリウム)
【緑肥植物の種類】

養分の足りない場所に植えるのが「マメ科」の植物
逆に、多すぎる養分を吸収してくれるのが「イネ科」の植物です
窒素分が過剰になると病害虫が発生しやすいので、イネ科を多めに混ぜます
- イネ科2:マメ科1
- 一年草1:多年草1
複数の緑肥作物を混ぜることで、土地に合ったものが残って育ちます
- イネ科の一年草:燕麦、ライ麦、イタリアンライグラス(2)
- マメ科の一年草:クリムソンクローバー(1)
- イネ科の多年草:オーチャードグラス(2)
- マメ科の多年草:赤クローバー(1)
イネ科は根を深く掘って土を耕す働きもします
●イネ科の一年草
例えば、燕麦(えんばく)は、オートミールの材料となるイネ科の一年草
冷涼な気候を好み、寒さに弱いので、種まきは暖地なら秋、寒冷地では春です
ライ麦は、パンやウィスキーの原料としても使われます
イタリアンライグラスは、ウサギやモルモットのエサにもなります
●マメ科の一年草
クリムソンクローバーは、真っ赤な花も可愛い草
●イネ科の多年草
オーチャードグラスは寒冷地でも育つので、北海道でも使われるイネ科の牧草です
●マメ科の多年草
赤クローバーは、ウサギやモルモットのエサになり、ハーブティーとしても使えます
通路に植えた多年草の緑肥作物が育つと、何年も草マルチとして使えます
害虫が緑肥作物のほうに集まることで、野菜を守る働きもします
【緑肥植物の植え方】

緑肥植物の種は、野菜や草花の種まきや植え付けをする「1か月以上前」にまきます
すると先に成長した緑肥植物が、土質を改良してくれます
例えば、緑肥植物を「野菜や草花の間」や「通路」に植えておきます
緑肥植物は、種や小さな苗を、鳥などから守ってくれる役割も果たします
輪作を続けているうちに地力が落ちてきたら「豆類」と混植します
そして養分が多くなりすぎた土には、イネ科を植えてリセットします
刈り取った地上部の緑肥は、地面に敷くと土の乾燥を防ぎます
自然栽培の肥料~堆肥

堆肥は植え付けする「1カ月以上前」に土に入れて馴染ませておきます
まず直径20cm×深さ20cmの穴を掘り、穴の底に一握りの完熟堆肥を入れます
そして土を埋め戻し、少し盛り上げておきます
盛り上げておくのは、植え付ける時に位置が分かりやすくするためです
少し離れた場所にも同様にして堆肥を入れておきます
離れた場所に肥料分があることで、さらに根を伸ばそうとするからです
堆肥は、枯草や野菜くずなどを使って作ることができます

堆肥を作る時に大事なのは、有機物を十分に「発酵」させることです。完熟していない堆肥を土に混ぜると植物の根を傷めることがあるからです。
完全に分解された完熟堆肥なら、植物の根を傷めることなく安心して使えます
【堆肥を作る土壌生物】
堆肥は、土壌生物たちのエサとなるものです
そのままでは植物の根が吸収することはできません
土壌生物に分解されて、初めて植物が吸収できる成分になります
土の中には、様々な土壌生物が棲んでいます
- 菌類(微生物)70~75%
- バクテリア(微生物)20~25%
- モグラ、ミミズ(土壌動物)5%以下
さらには生物の死骸も分解されて土の養分となります
そして微生物は、空気中の窒素を取り込んで植物に与える働きもしています
化学肥料や農薬を使わないのは、土壌生物を増やすためです
例えば、ミミズなどの土壌生物が土を柔らかくし、微生物が植物の養分を作り出しています
そして土の中に多様な生物がいれば、病原菌や害虫ばかり増えることはありません
一般的な畑の土には、100平方メートルあたり700gもの土壌生物が生息しているといいます
その700gの土壌生物たちに、様々な成分が含まれています
- 炭素(70g)
- 窒素(8g)
- リン酸(8g)
【自然栽培の関連記事】
のんびり、少量多品種を栽培する「自然栽培」は家庭菜園向きです
無農薬で育てた野菜を安心して食べられるのがメリットです

自然栽培や自然農法は、農薬や肥料を使わず、自然に委ねる栽培方法です。どちらも自然の生態系を活かす、という考え方が基本にあります。ただ放置するだけでは「農法」でも「栽培」でもありません。基本的な考え方と自然を理解したうえで、最低限の手入れは必要です。
自然栽培の家庭菜園では、最初の土作りが大切です
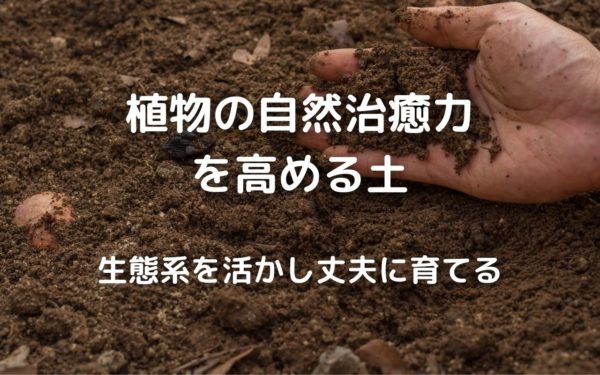
家庭菜園の土作りに最適なのが、秋です。なぜなら冬の寒さで病害虫を死滅させ、春までに土壌改良ができます。例えば、土を掘り起こし、堆肥を入れておくことです。土壌改良には時間がかかるため、植え付け1か月前には済ませておきます。そして野菜の収穫後は、足りなくなった養分を補う必要もあります。
自然菜園の具体例が豊富な竹内孝功さんの本を参考にしています
写真やイラストも豊富で分かりやすい本です
当ブログの記事を整理して電子書籍と紙の本で出版しています
Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください