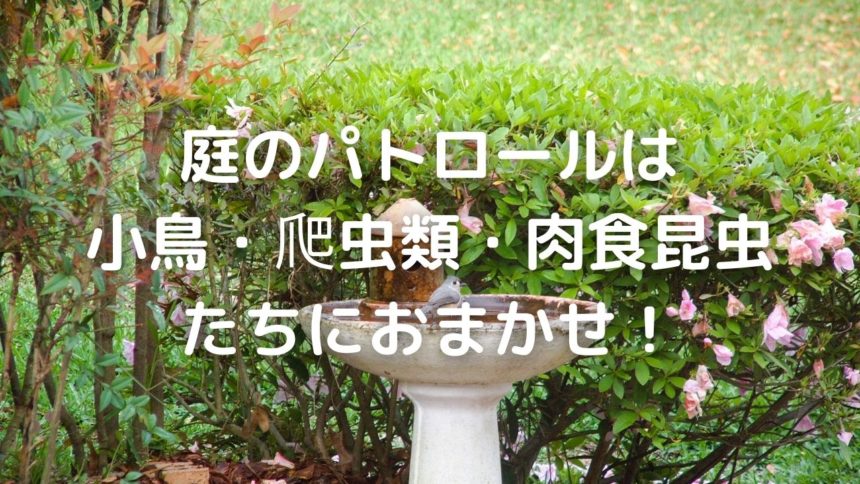害虫駆除は、天敵に任せるのが楽な方法です
なぜなら薬剤を使わなくても、天敵たちがセッセと虫を食べてくれるからです
例えば、庭や家庭菜園にやってくる「小鳥」たち
他には「肉食昆虫」や「爬虫類」も、虫は食べますが植物を食害しません
害虫を駆除してくれる天敵たちは、庭のパトロール役にピッタリです
害虫駆除してくれる天敵の種類

虫にとっては小鳥や爬虫類が天敵です
とはいえ害虫でも益虫でも、虫の種類に関係なく食べてしまいます
害虫を全て駆除しなくとも、植物が全滅するわけではありません
薬剤を使うと、益虫も天敵も、全て殺してしまいます
しかも薬剤に対する耐性が付くと、むしろ駆除しにくくなります
【アブラムシの天敵】
テントウムシがアブラムシを食べることは、よく知られています
成虫も幼虫も、テントウムシはアブラムシを主食としています
テントウムシが食べる量は少しだけとはいえ、いないよりはマシです
さらにはシロホシテントウやキイロテントウムシの大好物は、ウドンコ病だといいます
幼虫や卵の時の姿は害虫と間違えやすいので、知っておくと捕殺せずに済みます

テントウムシの幼虫も、植物は食べません
羽根がなくて飛べないので、一か所でセッセとアブラムシを食べてくれます
アブラムシを運んでくるのがアリです
アリはアブラムシを捕食する虫を追い払う代わりに、アブラムシから蜜をもらっています
ですからアリを寄せ付けないのが、アブラムシを寄せ付けない方法です
とはいえアリもアブラムシを食べることがあるといいます
「クサカゲロウ」や「ヒラタアブ」の幼虫も、アブラムシの天敵です
ヒラタアブは、アブではなくてハエの仲間
一見ハチに似ているものの、人を刺すことはありません

花の蜜を運び、受粉を助ける役割も果たします
【イモムシや毛虫の天敵】

イモムシや毛虫の天敵は鳥類やカエルなどの爬虫類
例えば、触れると痒くなるチャドクガの幼虫ですら、コゲラやカエルは食べてしまいます
アリやクモも蝶や蛾の卵や幼虫を食べます
蜂、寄生バエなどは、大きくなった幼虫を食べます
コマユバチは、チャドクガに寄生して殺してしまう蜂です
カマキリが食べるのは、蝶や蛾の成虫で、大きめのイモムシなども食べてくれます
肉食なので植物は食害しません

カマキリの卵は植物の枝に産みつけられ、マユのような糸に覆われています
ここからカマキリの赤ちゃんがゾロゾロ出てきて小さな虫を食べてくれます

【害虫を駆除してくれるハチたち】
アシナガバチもイモムシや毛虫を捕殺します
とはいえスズメバチの仲間なので、刺激すると人を刺します
毒性は少なく、刺されても死亡するケースはまれですが、一度でも刺されたら注意が必要です

スズメバチもアシナガバチも、刺激を与えなければ襲ってはきません
ですけれど巣に近づいたり、手で払ったりするのは危険です
ハチに遭遇した時には、なるべく静かに、身体を低くして、少しずつ後ずさりします
車や建物に入ってきた時には、慌てず騒がず、窓を開けると出ていきます
スズメバチは、ヘアトニックやスプレーの臭いに反応して攻撃してきます
ですからアウトドアでは付けないほうが安全です
それでも気づかず刺されてしまった場合には、刺された部分の毒を抜くのが応急処置
そのためポイズン・リムーバーを用意しておくと安心です
たとえ応急処置をしたとしても、必ず病院で手当てしてもらいます
蚊に刺された時にも、ポイズン・リムーバーで毒出ししておくと、痒みが軽減します
【カイガラムシの天敵】
駆除するのが難しいカイガラムシは、天敵に任せるのが一番
それがテントウムシ、クサカゲロウ、寄生バチ、蜂、鳥などです
カイガラムシはバラなどにこびりついて樹液を吸ってしまう害虫
硬い殻に覆われているため薬剤も効きません
だから歯ブラシでこそげ落とすくらいしかなく、大量に発生すると大変です
【テッポウムシ(カミキリムシ)の天敵】
カミキリムシの幼虫テッポウムシは、木の中に入り込んで食害してしまいます
このテッポウムシを殺してしまうのが寄生バチです
木の中に管を差し込み、幼虫に産卵して殺してしまいます
そのためテッポウムシに食害された木は、匂い物質を出して寄生バチを呼び寄せるといいます
【シロアリの天敵】
シロアリの天敵がアリ
アリの祖先はハチで、シロアリの祖先はゴキブリ
種類が違う虫です
シロアリが木を腐らせるわけではありません
腐りそうな木にシロアリが集まり、食害するのが被害の原因だそうです
害虫駆除をしてくれる小鳥を庭に呼ぶ方法

昆虫を主食としている小鳥が「シジュウカラ」「ヤマガラ」「コガラ」「ヒガラ」といったカラ類
ムクドリ、ウグイス、オオルリ、キビタキ、キツツキなども虫を食べています
完全に肉食なのが「モズ」や「ツバメ」です
特にヒナが生まれた時期には、セッセと虫を運んで食べさせています
とはいえ虫が少なくなる秋冬には木の実なども食べます
そのため柿やリンゴなどの果樹は、食害されてしまうこともあります
果樹の他に、小鳥が好む木の実があると、ある程度は防げるはずです
あるいは秋にバードフィーダーを設置してエサを与える方法もあります
【小鳥が好む木の実】
小鳥が好むのは「ナンテン」「アオキ」「ナナカマド」などの小さな実です
特にナンテンとアオキは、あまり大きくならないため狭い庭にも植えられます
南国向きなのがナンテンで、北国向きなのはアオキです
●ナンテン

メギ科ナンテン属の常緑低木で、樹高1~3mです
とはいえ暖地なら4~5mまで育つこともあります
暑さにも寒さにも強い木なので、本州より南なら地植えできます
濃い緑色の葉が枝先に集まって付きます
そして6月ころには円錐状の白い花がたくさん咲きます
晩秋から初冬には実がなり、10月には熟して赤くなります
園芸品種の葉が丸いオタフクナンテンは、実が付かず、葉が紅葉します
高さ50cmくらいなので、庭の下草として使うのに丁度いい大きさです
オカメナンテンとも呼ばれます
ナンテンは「難を転ずる」縁起の良い木としても知られ、庭の鬼門に植えたりします
福寿草と一緒に植えたり、玄関前やトイレ前などに植えたりすることもあります
贈答用の赤飯にナンテンの葉を乗せるのも縁起が良いためです
●アオキ

アオキ科アオキ属の常緑低木で、樹高2~3m
半日陰を好み、寒さに強い木です
枝も青いためアオキと呼ばれます
原産地は日本で、山地に自生しています
関東から西の沖縄まで生えている木です
葉は8~20cmの楕円形で、厚みがあり、光沢があります
3~5月には紫色の穂状の花が枝先に咲きます
そして秋には2cmくらいの卵型の実が赤く熟し、正月飾りなどに使えます
熟した実から採った種でも育てられ、枝を水に挿すだけで発根して挿し木にできます
雪が多い地方に最適なのが「ヒメアオキ」です
積雪に適応した変種で、本州北部から北海道の日本海側に自生しています
●ナナカマド

ナナカマドは寒さに強く、北海道の街路樹にも使われています
とはいえ樹高6~10mにもなる落葉高木です
そのため庭木にするなら「ナンキンナナカマド」「ニワナナカマド」が適しています
【バードフィーダー】

庭の果樹を小鳥から守りたい場合には、バードフィーダーにエサを置いておきます
あるいはピーナツを糸で繋げたリースを掛けておくのも有効です
ただしリスやネズミがやってくることもあります
【巣箱】
シジュウカラなどを呼ぶための巣箱は「直径2.8cm」の穴をあけておきます
3cm以上の穴を開けると、スズメなど他の鳥が入ってきてしまいます
巣箱の大きさは「幅15×奥行15×高さ20~24cm」くらい
床から15cmくらいの高さに穴をあけます
巣箱の底には水抜け用の穴も開けておくことが大事です
ヒナが巣立ったら中を掃除できるよう、開閉できるようにしておきます
秋~冬に設置しておくと、繁殖期の3~5月に小鳥が巣作りを始めます
設置場所は下枝が少なく真っすぐな木が良く、地面から150~250cm高さが適度です
ヘビが上っていかないよう、板やバケツなどを取り付けた上に設置すると安心です
ニワトリで害虫駆除

田舎の一軒家なら、ニワトリを飼ってみるのも楽しいものです
ニワトリは地面の虫も食べますが、特にハエの幼虫ウジムシが大好物
生ごみに湧くウジムシが減るので、ハエも少なくなるというメリットもあります
ニワトリは、エサを用意しなくとも、野菜クズや雑草だけで充分です
「メスのニワトリ」なら早朝に大声で鳴く習性もありません
生後5か月くらいから、2~3日に1個くらい卵を産みます
卵をいただき、害虫駆除もしてくれるのですから有難い存在です
ニワトリより小さなウズラでも、セッセと虫を食べてくれます
害虫駆除をしてくれる爬虫類

カエルやカナヘビは、地面に近い部分の虫を食べてくれます
益虫も害虫も構わず食べてしまいますが、葉を食害する虫を防ぐには心強い味方
特に発見しにくい低い場所にいる毛虫類を食べてくれるのはありがたい存在です
カナヘビは、ヘビではなくてトカゲの一種
頭から尻尾まで20~25cmくらいの小さな爬虫類です
可愛いヘビという意味でカナヘビと呼ばれています
葉や木の幹にも上っていけます
クモやワラジムシなど節足動物を食べています
カナヘビは北海道から九州まで日本全国にいますが、東京や千葉では絶滅危惧種です
殺虫剤などの薬品を使用すると、こういった爬虫類も減ってしまいます
害虫駆除に役立つ庭の環境つくり
病虫害が大量に発生するのは、環境が原因のこともあります
- 肥料が多すぎる場合
- 日当たりが悪い場合
- 風通しが悪い場合
- 薬剤を散布しすぎた場合
害虫が薬剤に抵抗力をつけてしまうと効かなくなります
そのうえ薬剤を使うことで、益虫まで殺してしまいます

家庭菜園や庭では薬品をあまり使いたくありません。安心して食べられる野菜を作りたい。子供やペットにも安全な場所にしておきたいからです。
コンパニオンプランツでも、ある程度の虫除けが可能です
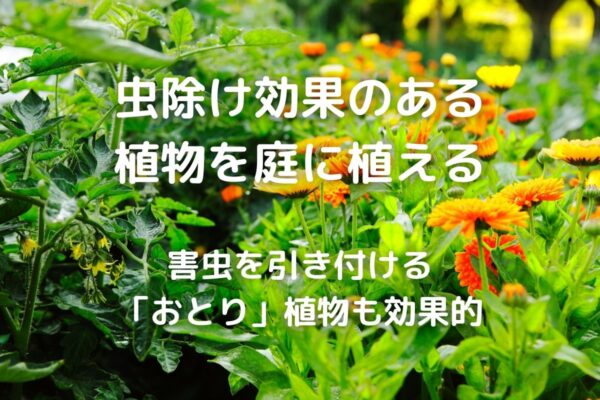
庭や菜園に植えた植物によって、害虫を防ぐことができます。虫によって、植物の好き嫌いがあるからです。例えば、ハーブの強い香りを嫌う虫は多くいます。
自然の生態系を活かし、植物が持つ本来の生命力を高めること
そうすれば少しくらい病虫害が発生しても広がることはありません
当ブログ記事を整理してアマゾンKindleの電子書籍と紙の本で出版しています
Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください