エディブルフラワーを加えると、料理の楽しさが広がります
なぜなら彩りとして飾ったり、お茶にして飲んだり、色と香りを楽しめるからです
例えばサラダに花びらを加えたり、酢の物や砂糖菓子などにもできます
さらに乾燥や酢漬けなど、保存食にしておくと季節を問わず花の料理を楽しめます
そして綺麗な花の中には、食べられるものが意外と多くあります
エディブルフラワーの料理

料理に使う花は、主に彩りと香りづけ
そのため火を通さないほうが色と香りを残せます
例えば「サラダ」や「酢の物」などです
日持ちしないので、その日に食べる分だけ作って食卓に出します
とはいえ見栄えがするので、パーティ料理などにピッタリです
【エディブルフラワーのサラダ】

特に花びらの綺麗な色を活かせるのがサラダです
例えば「たんぽぽ」は全草が食べられるので、黄色い花びらも使えます
春の柔らかな葉と花に、ルッコラなどを組み合わせるとよく合います

あるいはバラの花びらもサラダにピッタリです
おすすめは白バラやピンクのバラで、深紅のバラは苦みがあります

そして梅、桜、桃の花びらも使えます
エディブルフラワーとして食べるのは主に「花びら」の部分です
そして料理に使う場合には「食用」であることを確認することが重要です
例えば、お花屋さんで買った花は食べられません
食用花として市販されている物なら安心して食べられます
【エディブルフラワー酢の物】

たんぽぽは咲き始めが最も美味しい時期です
開ききる前の花びらをほぐして酢の物にすると、散らし寿司にも使えます
漬けこむと色が褪せるので、保存には向きません
熱湯にサッとくぐらせてから冷水に放して冷まし
ザルに上げて水気を切ってから三杯酢をかけます
- 酢(大さじ4)
- 醤油(小さじ1)
- 砂糖(大さじ1)
他の花びらにも応用できます
例えばデイリリーも「蕾」を摘み取って酢の物にできます

- デイリリーの蕾を茹でてガラス瓶に入れる
- クローブ、シナモン、ジンジャーを加える
- 塩とメープルシロップをかける
- ビネガーを注ぐ
デイリリーはユリのような野草ですが、ユリ科ではなくススキノキ科
別名「カンゾウ」「ワスレグサ」とも呼ばれ、本州より南の野原などに自生しています
ただし毒草「キツネノカミソリ」に似ていることには注意が必要です
キツネノカミソリは開花期、周囲の草が茂ってくると葉を落とすことが特徴
デイリリーは、花茎の根元に葉があることで見分けられます
【エディブルフラワーのバター】

花びらを混ぜ込んだバターは、パンやクラッカーに塗って食べられます
乾燥させた花を使い、バターにハチミツを混ぜても美味しくなります
香りのよいカモミールやラベンダーなら花の色と香りを楽しめます
エディブルフラワーを飾ったり、イチゴなどの果物やドライフルーツを乗せても綺麗です
【エディブルフラワーのクリームチーズ】

花びらをまぶしたクリームチーズは見栄えがするのでパーティ料理にもピッタリ
ラップで包んで冷蔵庫に入れておくと馴染みます
フラワーチーズにパンやクラッカーなどを添えて、ワインなどのおつまみにもなります
【エディブルフラワーの砂糖菓子】

デザートのトッピングにぴったりなバラの砂糖漬け
ヨーグルト、アイスクリーム、手作りケーキ、プリンなどの飾りつけに使えます
「グラニュー糖」をまぶすとキラキラし、「粉砂糖」を使うと柔らかな色合いです
まず花びらを水洗いして水気を切り、溶きほぐした「卵白」をブラシで塗ります
そして茶こしで砂糖を振りかけ、ザルなどに広げて乾かしたらできあがり
卵白を使うので長持ちしませんが、冷蔵庫で数日なら保存できます
アカシアやライラックのように小さな花なら、卵白の代わりに「シロップ」で
水やホワイトリカーに砂糖を溶かし、花房を浸してからザルに上げ、砂糖をまぶします
エディブルフラワーのドリンク

ドリンクに使うエディブルフラワーは彩りと香りづけ
見栄えがするので、お客さんが来た時に出すのにもピッタリ
ホームパーティでの話題作りにも役立ちます
【エディブルフラワーの花茶】

桜、梅、桃などの花を乾燥させ、花茶にすると綺麗
ガラスのティーポットに入れて、じんわり色が出てくるのを待ちます
乾燥させた花びらは、ガラス瓶に入れて保存しておいても綺麗
摘み取った花をザルなどに広げ、風通しが良く直射日光が当たらない場所で乾燥させます
【エディブルフラワーのリキュール】

梅酒を作るようにして、花を氷砂糖とホワイトリカーに漬けこんでリキュールにできます
蜂蜜やメープルシロップを加えたり、ワインやブランデーに漬けたり、アレンジも可能です

乾燥した葉や花ならいつでも作れます
生の葉や花なら摘み取ってすぐ漬けこみます
「生花300g:アルコール1800㏄」または「乾燥花150g:アルコール1800㏄」くらいの割合
花びらの半量から同量くらいの氷砂糖を交互に重ねながら瓶に入れ、アルコールを注ぎます
ときどき混ぜながら2~4カ月くらい冷暗所に置き、氷砂糖が溶けたら飲めます
ザルなどで濾し、液体だけ密閉容器に入れて常温または冷蔵庫で保存
長く漬けるほど濃いエキスになり、炭酸で割ると、より香りが立ちます
取り出した花や葉は入浴剤などに使えます

タンポポワインは、花びらを洗ってから3~4時間ほど日に当てて乾燥させてから瓶詰めします
花びらの2倍の量の「焼酎」に5~6日ほど浸け、濾して花びらを取り除き、3~5カ月おいたら飲み頃です
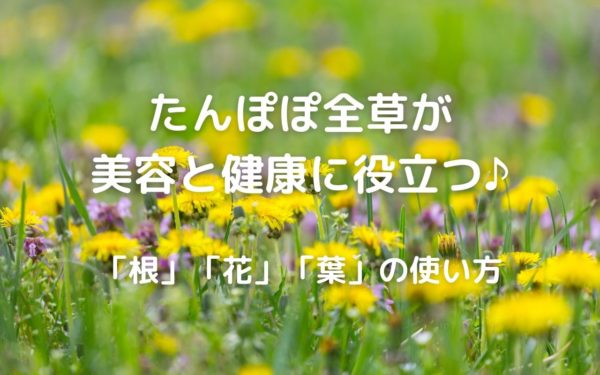
たんぽぽは「蒲公英(ほこうえい)」と呼ばれ、生薬として使われる薬草。根、葉、茎、花、全草が利用できます。薬効には「美肌」「健胃」「胆汁分泌」などがあります。花や葉は食用にも使え、根はたんぽぽコーヒーにできます。地中に深く伸びる根は養分を地表へと運ぶ役割も果たしています。
【エディブルフラワーのアイスキューブ】

製氷皿に、花びらと水を加えて氷にしておくと、冷たいドリンクに使えます
花びらの色が活かせる、透明な氷を作るポイントは2点です
- 水に不純物が含まれていない
- ゆっくり凍らせる
不純物のない水は、「蒸留水」を使うか、水を「沸騰」させます
硬度の高いミネラルウォーターは不向きです
ゆっくり凍らせるには、まず冷凍庫の設定温度を下げます
そして製氷皿の下に「割り箸」や「発泡スチロール」を敷きます
さらに丸い氷をつくれる製氷器を使うと、ゆっくり氷が溶け、ドリンクが水っぽくなりません
エディブルフラワーの保存食

食べられる花は、野菜やハーブと同じように保存が可能です
例えば「乾燥」「塩漬け」「酢漬け」「シロップ漬け」「味噌漬け」など
ガラス瓶に入れておくと、飾っても綺麗です
【エディブルフラワーの乾燥】

花や葉を水洗いしてから平たく並べたり、茎を束ねて吊るしたりして風通しの良い場所で乾燥させます
そしてパリパリに乾いたら密閉容器に入れて保存
長期保存ができ、お茶や入浴剤として使ったり、水で戻してスープの具に使ったりできます
【花びらのジャム】

たんぽぽ、カモミール、バラ、アカシアなどは花びらをジャムにできます
まず花を水洗いしてザルに上げ、鍋に入れて水を注ぎ、火にかけます
いったん花びらを取り出してザルで濾し、鍋の液体に砂糖を加えて煮溶かします
それから花びらを戻し入れ、煮詰め、最後にオレンジの皮をすりおろして加えます
瓶詰めしておくと紅茶に入れたり、パンに塗ったり、フルーツジャムと同じように使えます
【花びらシロップ】

バラ、ライラック、ラベンダーなど色が綺麗な花は、シロップにしておくと便利
炭酸で割ったり、お茶に入れたりしてドリンクにできます
たっぷりの花びらを水洗いしてザルに上げ
瓶に入れて砂糖と熱湯を注ぎ、毛布などで包んで十分に色が出たらザルに上げて液体だけ瓶づめします
さらに砂糖とレモン汁を加えて煮詰めると、パンケーキなどにかけるソースにできます
【花びらの塩漬け】

七分咲きの八重桜または枝垂桜は、花を軸ごと摘み取ります
そして桜の3~4割ほどの塩を振り、桜が浸るくらいのレモン汁または梅酢を加えます
重石をして1週間ほどおいてからペーパータオルの上に広げて水気を切り、2~3日ほど陰干ししたら完成
ヨーグルトやアイスのトッピング、クッキーやケーキの飾りに
鯛めしやおにぎりに混ぜたり、吸い物の具にしたり、様々な使い方ができます
【花びらの味噌漬け】

タンポポの花を味噌漬けすると、野菜スティックのソースや御飯のおかずにピッタリです
瓶などに入れ、冷蔵庫で保存できます
まず花びらをサッと茹で、冷水にくぐらせ、冷ましてからザルに上げます
そして20分くらいおいて水気を切ります
みりん、酒、味噌を混ぜ合わせ、水気を切った花びらを加えて混ぜて保存
食べられる花には色んな種類があります。

パーティ料理にピッタリなのがエディブルフラワーを使った料理。花びらの色や香りが食卓を華やかに演出してくれます。例えば「バラ」は代表的なエディブルフラワーです。
ただし観賞用の花の多くは食べられません
中には死に至るほどの猛毒を持つ植物もあるので注意が必要です
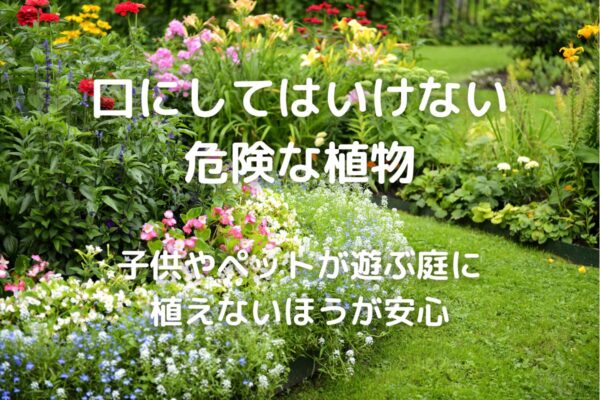
野菜やハーブであっても、部位によっては食べられません。薬草や生薬に使われている植物でも、食べすぎると中毒を起こすことがあります。植物を見分けられず、正しい知識を持たずに、野草を食べるのは非常に危険です。






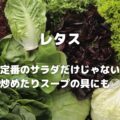

AmazonUnlimitedから来ました。
とても良かっです。、えっ食べれるの?
とかなり驚きました。
特にたんぽぽとライラックがお気に入りです。道民です。来年食べてみます。
ライラックは購入し植えることにしました。
たんぽぽワインの
もっと時間と手間をかけるとぐっと美味しくなります〜で質問があります。
砂糖などの分量が50gとありますが、たんぽぽの花の量はどれぐらいですか?
あと、お酒はいついれるのですか?
【雑草】春たんぽぽを収穫して薬草として活用
https://kimirin.wp-x.jp/spring-dandelion-herb
にレシピを書きましたので、こちらにも転載しておきますね。
簡単レシピはこちら
1.タンポポの花びらを洗い、3~4時間日に当てて乾燥させる
2.花びらの2倍の量の焼酎に5~6日ほど浸ける
3.濾して花びらを取り除き、3~5カ月おいたら飲み頃
(乾燥させた花びらを瓶などに入れたら、2倍の焼酎を入れます)
美味しいレシピはこちら
(たんぽぽの花は100g、こちらはお酒を入れません)
1.「たんぽぽ花(100g)」を耐熱容器に入れ「熱湯(100㏄)」を注いで蓋をする
2.毎日1~2回くらい混ぜ、5日ほど経ったらザルに上げて濾して液体だけ鍋に入れる
3.「砂糖(50g)」「みじん切りオレンジかレモン(5g)」「レーズン(50g)」を加える
4.強火にかけて沸騰させ、20分くらい煮てから耐熱容器に入れる
5、冷めてから「トーストした食パン(1枚)」と「ドライイースト(1袋)」を加える
6.きっちり蓋をすると発酵して瓶が割れることがあるので「布」をかぶせて3~7日おく
7.布巾を敷いたザルに上げて濾し、保存瓶に入れて冷暗所に置く