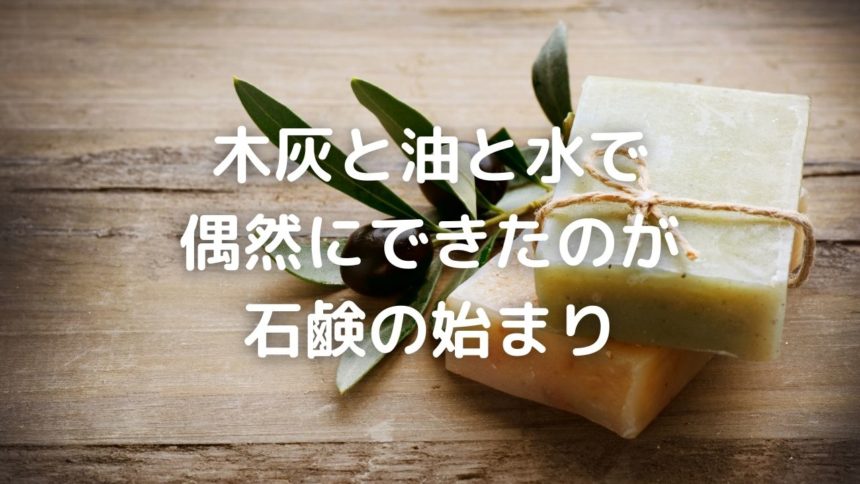石鹸の作り方を発見した、サポー山の物語がローマの伝説にあります
サポーは「石鹸」を意味するラテン語で、それが石鹸成分「サポニン」の語源です
伝説によると、山の上の祭壇に生贄が捧げられ、燃やされた後、大雨が降りました
すると川下で洗濯をしていた人たちが、汚れ落ちが良くなることに気が付きます
その要因が、動物の「脂肪」、祭壇の「灰」、焼いた時の「熱」、雨による「水」
それで石鹸の原料が「油」「アルカリ」「水」であることが分かりました
基本的な石鹸の作り方

開拓時代のアメリカで、石鹸作りは、家庭の主婦が行っていた家事のひとつでした
当時は牛脂に木灰と水を混ぜて作っていたといいます
現在の石鹸は原料も製法も洗練されていますが、石鹸作りの基本は変わりません
まず手作り石鹸で大切なのが「鹸化」という工程です
鹸化とは、油脂とアルカリに熱と水を加えて分解すること
そして本来は混じり合わない「水」と「油」を混ぜて固めるのがアルカリの役割です
伝説では「動物の脂肪分」が油脂、祭壇の「木材が焼けて灰になったもの」がアルカリです
【アルカリで鹸化させる】
手作り石鹸では「苛性ソーダ」のアルカリがよく使われます
とはいえ苛性ソーダは、薬局でしか購入できない劇薬で、廃棄するにも配慮が必要です
その点、安心して使えるのが昔ながらの「木灰」
ところが現在の都会では、草木を燃やすことすら難しく、木灰は手に入りにくい素材です
その木灰と同じ成分なのが「炭酸カリウム」です
こんにゃく作りなどに使われる食品添加物なので、安心して使えます
【アルカリを扱う時の注意点】
注意点は、アルカリ性の強い物質は「プラスチック」「アルミニウム」「スズ」を腐食させること
そのため石鹸作りの際は「道具の素材」に注意が必要です
例えば「木」「紙」「ガラス」「エナメル」「ステンレス」「陶器」などが適しています
【手作り石鹸の道具】
手作り石鹸に必要な道具は、以下のようなものです
- 灰汁液を入れる「容器」(ガラス瓶や牛乳パックが注ぎやすい)
- 油脂と灰汁を混ぜる「鍋」(10~12リットルくらいの大きさ)
- 灰汁液と油脂をかき混ぜる「木べら」
- 食品用の「温度計」(灰汁用、油用、2本あると良い)
- 手荒れを防ぐ「ゴム手袋」
- 石鹸液を固める「型」(内側にワセリンなどの油を塗っておく)
- ダンボール、発泡スチロール、毛布などの「断熱材」
- 作業面や床を保護する「紙」(新聞紙や障子紙など大きなもの)
使った道具類は、キッチンペーパーでよく拭き取ってから「酢」で中和します
その後で食器洗剤で洗っておくとアルカリ成分を除去できます
型として使えるものは身の回りにたくさんあります
- ガラスや陶器の灰皿
- 紙製の箱
- 木箱
- 貝殻
- 卵の殻
【手作り石鹸の材料】
石鹸作りの「油」は動物性、植物性、ほぼ何でも使えます
水は「軟水」が望ましく、集めた「雨水」も使えます
硬水の場合は「ホウ砂」を大さじ2杯ほど加えると調整できます
石鹸の作り方手順

- 「油脂」と「灰汁液」を入れた容器をそれぞれ湯か水につけて「35~36℃」にする
- 混じりやすくするため、油脂を均等に円を描くようにかき混ぜながら、灰汁液を一定の早さで注ぐ
- 不透明なブロンズ色が次第に薄くなり、表面がサワークリームくらいの固さになればOK
- 着色料や香料などを加え、型に流し込み、暖かい場所に置く
- 型を段ボール、スチロール、毛布などで覆う
- 24時間後に型から石けんを取り出す
- 風通しの良い場所に2週間から4週間おいて空気に触れさせる
着色料や香料を先に入れると鹸化を妨げるので、型に入れる直前に加えます
【灰汁液と油脂の温度】
鹸化させるには、灰汁液と油脂の「温度」に注意が必要です
最も簡単な方法は、灰汁と油脂の両方を35~36℃にしてから混ぜ合わせること
灰汁より油脂の温度を高くすると良いとも言われます
- 牛脂を使う場合は、油脂52℃、灰汁34℃
- ラードを使う場合は、油脂28℃、灰汁23℃
- 牛脂とラード半々の場合は、油脂41℃、灰汁28℃
【アルカリと水を混ぜる】
まず容器にアルカリの結晶と水を入れてかき混ぜます
するとアルカリと水が反応して100℃以上の高温になります
結晶が完全に溶けて「50~80℃」くらいになるまで冷ましておきます
動物性油脂を使う場合は、あらかじめ湯煎で溶かしておきます
そしてアルカリ溶液と油を40℃くらいにします
次に油にアルカリ溶液を少しずつ入れながら混ぜ、30分くらいかき混ぜ続けます
容器にラップをかけて30分ほどおくと、とろみが出てきます
その間にも時々はかき混ぜて様子を見ます
【分離した油脂とアルカリの再生法】
混ぜた時に鹸化せず、脂肪が上に浮いてアルカリが沈み、分離することがあります
木べらで静かにかき混ぜながら「60℃」に加熱すると再生が可能です
火からおろして攪拌を続けると固まってきます
さらに3~15時間ほど経つと、マヨネーズくらいの硬さまでとろみがついてくるはずです
そして木べらを持ち上げて数滴ほど垂らした時、1~2滴が浮くようならOK
スプーンですくった時に、スプーンにくっつかないくらい固まったら型に入れます
【型に入れて固める】
型に入れたら箱などに入れて保温し、「24時間」おいてから保温箱から出します
そして室温に「数日から1週間」ほどおいたら型から出します
例えば、牛乳パックの型ならカッターで切れるので出すのが楽です
最後に型から出して1週間くらい乾燥させ、好みの形や大きさに切ります
さらに「1カ月」くらい空気に触れさせておくと手作り石鹸の完成です
石鹸の作り方レシピ

使用する油脂の種類や、油脂・灰汁・水の配合によって様々な石鹸になります
最も作りやすいのは牛脂とラードを半々に使う組み合わせです
そして手作り石鹸の標準的なレシピは「油脂(220g):水(100ml):灰汁(30g)」
これで固形石鹸を3~4個ほど作れます
色々な香りや色などを試したい場合は、1個ずつ作る方が簡単で経済的です
例えば、1個の石鹸に必要な材料が以下になります
- 軟水(1/2カップ)
- 溶かした牛脂(1カップ)
- 灰汁(大さじ山盛り2杯)
水に灰汁をゆっくり加えて灰汁溶液を作ります
まず灰汁液と油脂それぞれ体温程度に温め、ガラスのボウルなどに入れます
そして、ゆっくり泡だて器で混ぜて、サワークリームくらいの硬さにします
次に型に流しいれ、24時間おいたら型から出して2~4週間くらい熟成させます
型から出した段階では、まだ柔らかい状態なのでナイフで切ったり、丸めたり、形を変えることができます
とはいえ、まだ石鹸になっていないので、ゴム手袋をして作業しないと手荒れします
そして「空気に触れさせる」ことによって石鹸に変わり、肌への刺激がなくなります
【手作り石鹸に使う油脂】
石鹸作りに使える油脂は、動物性脂肪や、多くの植物油
特に牛脂と豚脂(ラード)が最も作りやすい基本的な手作り石鹸です
あるいは羊毛の油脂を精製したラノリンも使えます
こちらの↓ショップには苛性ソーダを使った石鹸つくりが紹介してあります
鶏脂や植物油だけでは柔らかすぎるので、他の油脂と組み合わせます
ココナツオイルは高品質の食器洗剤や化粧石鹸になります
ヤシ油の石鹸は優しく心地よい香りがします
大豆油、綿実油、トウモロコシ油、ピーナツ油は泡立ちの少ない石鹸になります
適切に処理すれば、揚げ油などをリサイクルして手作り石鹸にできます
油に同量の水を加えて鍋に入れ「塩(大さじ2)」を加え沸騰させます
火からおろして混合物の1/3量くらいの冷たい水を加えと、混合物は3層に分離します
一番上に浮く純粋な油脂だけすくい取って石鹸作りに使います
匂いがある場合には「酢1:水5」の割合で加えて分離させます
分離後の油脂1300gにスライスしたジャガイモ1個を入れて火にかけても脂の匂いが取れます
【スキンケア効果の高い石鹸】
手作り石鹸には様々な美容成分や香り、色を加えることができます
石鹸に加えるものによって、肌タイプに合わせた石鹸が作れます
油分を多くするほど肌に優しい石鹸になります
基本の石鹸:硬い石鹸
- オリーブオイル(700g)
- 牛脂(1640g)
- 灰汁(300g)
- 水(950ml)
アボカド石鹸:敏感肌用
- アボカドオイル(170g)
- オリーブオイル(530g)
- 牛脂(1640g)
- 灰汁(300g)
- 水(950ml)
ココナッツとオリーブ石鹸:冷水でも濃厚でやさしい泡立ちの石鹸
- オリーブオイル(650g)
- ココナツオイル(650g)
- 牛脂(650g)
- 灰汁(43g)
- 水(950ml)
パーム石鹸:乾燥肌用
- ラード(1360g)
- ヤシ油(450g)
- オリーブオイル(900g)
- 灰汁(370g)
- 水(1200ml)
ミルクとハニーソープ:肌に栄養を与える石鹸
型に流しいれる直前に、混ぜた粉ミルク(28g)とハチミツ(28g)を加えます
ローズウォーター石鹸:やや収斂性のある脂性肌用の石鹸
灰汁を混合する時の水の一部をローズウォーター(110g)に置き換えます
ローズウォーターは化粧水としても使える無添加がおすすめです
蒸留器を使ってローズウォーターを作ることも可能です
脂性肌用にスクラブ効果を加えるなら粒状の穀類を加えます
「アーモンドミール」「オートミール」「コーンミール」など
●ブロンド用シャンプー
カモミール、モウズイカの花、マリーゴールド
それぞれ浸出液85gを型に注ぐ前に加えます
●黒髪用シャンプー
ローズマリー、ラズベリーの葉、レッドセージ
それぞれ浸出液85gを型に注ぐ前に加えます
【香りの良い石鹸】
石鹸に香りをつけるには、型に入れる直前にエッセンシャルオイルを加えます
例えば「シナモン」「ベイベリー」「ローズマリー」「ジャスミン」「カーネーション」
市販の香水は、含まれているアルコールが鹸化を妨げるので使えません
ハーブや花を沸騰した湯に浸して茶こしで濾した浸出液も使えます
石鹸レシピの水を浸出液に置き換えるだけ
十分に濃い浸出液なら、型に注ぐ直前に加えてもOK
香りづけは、基本レシピの分量に対して大さじ3杯くらいで十分です
【手作り石鹸の着色】
着色剤として使えるのは、植物の根、樹皮、葉、花、果物、野菜など
ターメリックなどスパイスに使われる天然染料なら型に注ぐ直前に入れられます
染料に沸騰させた湯を注いで濃い色を出し、濾して100~300gくらいを加えます
キャンドル用の染料も使えますが、食品用の着色料は石鹸とうまく混ざりません
着色料を静かにかき混ぜると大理石模様にすることもできます
石鹸作りの灰汁の作り方

伝統的な灰汁の作り方は「木灰」から灰汁を浸出する方法です
この方法で生成された灰汁がカリで、主成分は炭酸カリウム
これは市販の苛性ソーダより腐食性の低い物質です
【灰汁つくりの材料】
広葉樹の木灰なら何でも使えます
オーク、ヒッコリー、サトウカエデ、果樹、ブナの灰が特に適します
【灰汁の作り方】
灰汁作りに使うのは、大きな「木製の植木鉢」や「ワイン樽」などです
そして底面に穴が開いていて、浸出した液体を取り出せるものが適しています
水が浸透する灰が多いほど灰汁の溶液が濃縮されます
そのため大きな容器が適しています
例えば、2個の「ブロック」の上に鉢や樽を置き、下に溶液を受ける「器」を置きます
まずは溶液に灰が入らないよう、底に「藁」などを敷き詰めてから木灰を詰めます
次に灰の上部にくぼみを作り、水が2~3リットル溜まるようにします
そのくぼみに「沸騰させた水道水」や「雨水」を満たし、ゆっくり浸透させます
水が全て浸透したら、さらに水を追加します
灰汁が底穴から滴り落ちるまでには時間がかかります
しっかり詰まった灰なら「数日」かかりますが、急いで水を追加せず、待つことが大事です
器に受けた灰汁に「生卵」を割り入れてみて、卵が浮かないようならOK
【灰汁溶液の結晶化】
灰汁溶液からでも石鹸は作れますが「結晶」にしたほうが作りやすくなります
ステンレスやエナメルの鍋に入れて煮詰めることで、灰汁溶液を結晶化できます
最初は黒い固形物になり、加熱し続けると不純物が取り除かれて灰白色のカリが残ります
【掃除に使える灰汁】
石鹸になっていないアルカリ溶液のままの灰汁には殺菌力があります
そのため床掃除などに使うとカビ予防になります
例えば、わざわざ石鹸にしなくても、掃除に使うだけなら灰汁でも充分に使えます
ただしアルカリ溶液は肌への刺激が強すぎるので、油分を加え、鹸化させます
植物油も手作りできます

植物油は、多くが「種」から採ったものです。種子を保護している硬い部分の「核」から採れる油もあります。オリーブやアボカドなどは、果実に油が含まれている植物です。
当ブログ記事を整理してアマゾンKindleの電子書籍と紙の本で出版しています
Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください